社内コミュニケーションツールおすすめ10選!選び方や導入効果を解説

現代のビジネス環境、特にコロナ禍以降の状況下において、ITツールを駆使した社内コミュニケーションの質とスピードは、よりいっそう厳しく問われるようになってきました。
リモートワークやハイブリッド型勤務の普及により、「社員同士が気軽に相談できない」「情報が散らばって見つからない」「意思決定が遅れる」といった課題が、これまで以上に多くの企業で顕在化しているからです。
そんな中、いま注目されているのが「社内コミュニケーションツール」です。
組織は「社内コミュニケーションツール」を活用することで、オンライン会議・チャット・ファイル共有・ナレッジ管理などを一元化することができます。
したがって、現在多くの企業がその新規導入や見直しをはかっています。
この記事では、社内コミュニケーションの課題を解決するおすすめのツール10選と、導入に際する選び方・注意点・導入効果までを詳しく解説していきます。
社内コミュニケーションツールの導入を検討している経営者やマネージャー、現場社員の方はぜひ参考にしてみてください。
目次
社内コミュニケーションツールおすすめ10選

社内コミュニケーションツールと一口に言っても、その機能や強みはツールごとに異なっています。
チャット・会議・タスク管理・ナレッジ共有など、自社の目的に最も適したツールを選択することが、課題の解決やコストパフォーマンスの最適化に向けて不可欠となります。
ここでは、国内外で評価の高い10のツールを厳選し、その特徴を紹介していきます。
Talknote
Talknoteは、「組織の健康状態を“見える化”する社内SNS」です。
メッセージや掲示板機能に加えて、コミュニケーション量や反応率を自動解析し、離職リスクやチームの停滞を早期に把握できるのが特徴です。
また社内の会話だけでなく、勤怠連動による稼働状況の可視化や、承認・報告フローの簡略化も可能となっています。
スマホアプリも用意されており、手軽にリアルタイムで情報共有をできることも嬉しい点です。
これらの特徴から、特に「組織の状態をデータドリブンに管理し施策へと繋げたい」というニーズをもった企業に最適なツールであると言えます。
基本的な料金プランは、年間契約一括払いで1ユーザーライセンス1,180円/月、1アルバイトライセンス580円/月、月契約月々払いで1ユーザーライセンス1,380円/月、1アルバイトライセンス680円/月となっていますが、エンタープライズプランや初期費用も存在するため、詳細は問い合わせをする必要があります。
TUNAG
TUNAGは、「制度運用と文化醸成を1つにまとめるエンゲージメントプラットフォーム」です。
社内制度・福利厚生・マニュアル・アンケートなどを集約し、制度が形骸化せず活用され続ける環境を親しみやすいUIで提供してくれるのが強みです。
サンクスカードや社内ニュース配信、誕生日メッセージなどの機能で、従業員同士の心理的距離を縮めることもできます。
申請や承認はPC・スマホの両方から可能で、現場作業員もアクセスしやすい設計となっています。
したがって、コミュニケーションと業務フローを一元化し、企業文化の浸透とエンゲージメント向上を同時に実現してくれる強力なツールであると言えます。
料金体系は「初期費用」+「月額費用」の構成ですが、それぞれの価格は利用人数や活用方法により変動するため、問い合わせが必要です。
LINE WORKS
LINE WORKSは、「慣れ親しんだLINEの操作感でビジネスを加速」してくれるコミュニケーションツールです。
ビジネス用のチャット、掲示板、カレンダー、タスク管理機能を搭載し、LINEの直感的なUIで誰でもすぐに使いこなすことができます。
外部のLINEユーザーや取引先とも安全に連携でき、業務連絡をスムーズにしてくれます。
また、音声・ビデオ通話、ファイル共有、アンケート機能も標準搭載しているため、基本的なコミュニケーションは問題なく網羅しています。
さらに特徴的なのは、スマホ完結型の運用が可能となっていることです。
現場職や外回りスタッフの情報共有にも最適なつくりであるため、特に「ITツールが苦手な社員が多い企業」にフィットすると言えるでしょう。
料金体系は、30人までのフリープラン(無料)、スタンダードプラン(1ユーザー540円/月)、アドバンストプラン(1ユーザー960円/月)の3つが存在します。
また年額契約をすると20%割引となります(スタンダードプランは1ユーザー450円/月、アドバンストプランは1ユーザー800円/月)。
30日間の有償プラン無料トライアルも用意されており、試験的に運用してみたい企業にも親切なサービス設計となっています。
WowTalk
WowTalkは、「国内開発×高セキュリティで守るビジネスチャット」ツールです。
国産ならではのきめ細やかなサポートと、端末紛失時のリモートワイプ、アクセス制限などの高度なセキュリティ機能が強みです。
チャット、通話、掲示板、タスク管理に対応し、スマホでもストレスなく操作可能です。
また業務とプライベートを分けたメッセージ管理や既読機能があり、情報漏えいリスクを低減してくれます。
医療・金融など機密性の高い業界での導入実績も豊富で、安全性重視の企業に最適です。
料金体系はシンプルプラン(1ID360円/月)、スタンダードプラン(1ID500円/月)、カスタマイズプラン(企業ごとに設定)が存在します。
シンプルプラン、スタンダードプランは30IDからの契約となっており、カスタマイズプランは1,000IDからの契約となっています。
Chatwork
Chatworkは、「日本企業の業務フローにフィットする定番チャット」ツールです。
チャット、タスク管理、ファイル共有を一体化した国産ツールであり、プロジェクトごとにグループを作成、社内外のメンバーを安全に招待可能です。
日本語UIで操作がわかりやすく、メールよりスピーディなやり取りを実現してくれます。
既読・未読管理やタスク期限設定など、日本企業の業務習慣に沿った機能が豊富に搭載されており、中小企業から大手まで導入実績が多く、コストパフォーマンスにも優れています。
組織人数100人・組織外ユーザー20人/1ユーザー・データ容量10GBまでなら無料で使用することができます。
そのほかにも、ビジネスプラン(月間契約の場合:1ユーザー840円/月、年間契約の場合:1ユーザー700円/月)、エンタープライズプラン(月間契約の場合:1ユーザー1,440円/月、年間契約の場合:1ユーザー1,200円/月)が存在します。
Slack
Slackは、「世界基準のチームコラボレーションハブ」ツールです。
チャンネルベースで会話を整理し、外部アプリ連携(Google Drive、Trello、GitHubなど)が豊富なグローバルスタンダードのチャットツールです。
メッセージ検索精度が高く過去の情報をすぐ引き出せたり、ワークフロー自動化やBot活用もできるため、柔軟に作業効率を向上させることができます。
また英語UIにも対応しており、多国籍チームやリモート環境にも適しています。
情報が散らからない優れた構造とUIが、長期的な業務の生産性向上を実現してくれます。
料金はフリープラン(無料)、プロプラン(月間契約の場合:1ユーザー1,050円/月※最初の3ヶ月は525円/月、年間契約の場合:1ユーザー925円/月)、ビジネスプラン(月間契約の場合:1ユーザー2,160円/月※最初の3ヶ月は1,080円/月、年間契約の場合:1ユーザー1,920円/月)と、カスタマイズ設計のエンタープライズプランが存在します。
NotePM
NotePMは、「社内の知識を資産化するナレッジ共有ツール」です。
社内マニュアル、議事録、報告書などの文書を階層構造で整理できるWiki型のツールとなっており、タグ検索や全文検索で必要な情報にすぐアクセスすることができます。
アクセス権限設定や変更履歴管理により、情報の正確性とセキュリティを確保することも可能です。
画像・動画の添付も容易にでき、視覚的にわかりやすい資料作成を実現してくれます。
属人化の防止や新人教育の効率化に強く、ナレッジマネジメントを重視する企業に適しています。
料金体系は編集ユーザー・閲覧ユーザーの数によって段階的に設定されており、最も安いプランは編集8名・閲覧24名からなる計32名までの4,800円/月のプランです。
Notion
Notionは、「あらゆる情報を一元管理するオールインワンワークスペース」です。
メモ、タスク、データベース、Wikiなどを自由に組み合わせて使える高自由度ツールとなっており、スタートアップ企業を中心として近年注目を浴びています。
ドラッグ&ドロップでレイアウトを直感的に変更でき、議事録やロードマップ、タスク進行管理まで一括対応することができます。
テンプレートも豊富で、チームやプロジェクトに合わせたカスタマイズが可能となっています。
個人利用から企業利用まで幅広く対応し、情報の一元管理を実現します。
料金体系はフリープラン(無料)、プラスプラン(月間契約の場合:1ユーザー2,000円/月、年間契約の場合:1ユーザー1,650円/月)、ビジネスプラン(月間契約の場合:1ユーザー3,800円/月、年間契約の場合:1ユーザー3,150円/月)、エンタープライズプラン(カスタマイズ設計)が存在します。
Google Meet
Google Meetは、「GoogleサービスとシームレスにつながるWeb会議」ツールです。
GoogleカレンダーやGmailと連動し、URLワンクリックで会議に参加できるビデオ会議ツールとなっています。
ブラウザから利用でき、アプリインストールは不要です。
最大100人までの無料会議、画面共有、リアルタイム字幕、ノイズ抑制などを搭載しており、教育現場や日常業務への導入が容易で、Google Workspaceユーザーなら追加コストなく利用可能です。
Zoom
Zoomは、「安定性と機能性で選ばれるオンライン会議の定番」ツールです。
ブレイクアウトルーム、録画、バーチャル背景、ウェビナー配信など機能が豊富なビデオ会議ツールとなっています。
低帯域でも安定した接続が可能で、音声・映像品質が高い点が評価されています。
また教育・医療・ビジネスなど幅広い分野で導入され、参加者の規模や用途に合わせて柔軟にカスタマイズ可能な点も便利です。
リモートワークやオンラインイベントの基盤として多くの企業に定着しています。
料金体系は、ベーシックプラン(無料)、99名までのプロプラン(月間契約の場合:1ユーザー2,549円/月、年間契約の場合:1ユーザー1,999円/月)、250名までのビジネスプラン(月間契約の場合:1ユーザー3,299円/月、年間契約の場合:1ユーザー2,749円/月)が存在します。
社内コミュニケーションツールの選び方4選

社内コミュニケーションツールは、導入する目的や運用体制に応じて最適なものを選ぶことが重要です。
ツール選びを誤ると、機能過多で使われなかったり、逆に必要な情報が共有されなかったりする可能性があります。
ここでは、導入前に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
導入する目的に合わせて選ぶ
社内コミュニケーションツールを導入する際は、まず「何のために使うのか」を明確にすることが大切です。
例えば、「ナレッジ管理」を強化したい場合には「情報を整理・蓄積しやすいツール」が適しており、「日々の業務連絡を効率化」したい場合には「チャット機能や通知機能」が充実したツールを選択するといいでしょう。
このように目的をはっきりさせることで、無駄な機能に悩まされたり過剰なコストがかかるのを防ぐことができます。
目的別に機能を見極めることで、導入後の運用がスムーズになり、社内全体での活用率も向上します。
直感的で使いやすいツールを選ぶ
どんなに高機能なツールでも、操作が複雑で使いにくければ現場で定着しません。
シンプルで直感的に操作できるツールは、導入後すぐに社員が使いこなすことができるため、定着率が高まります。
また、従業員のITリテラシーに合わせた選定も重要です。
初心者でも迷わず操作できるか、メニューや画面構成は分かりやすいかを確認しましょう。
操作性に優れたツールは、業務効率化だけでなく、社内コミュニケーションの活性化にもつながります。
無料版で試してから本格導入する
社内コミュニケーションツールの導入は、まず無料版やトライアル版で実際の業務に使用してみることが推奨されます。
実際に運用してみることで、自社の業務フローに適しているか、使い勝手は良いかを現場の使用感覚と照らし合わせて検証することができるからです。
無料版で問題点や改善点を洗い出し、必要に応じて有料プランへ移行することで、コストを抑えつつ最適な運用をすることが可能となります。
このステップをきちんと踏むことで、導入後のトラブルや不満を大幅に減らすことができます。
連携できる外部ツールを確認する
社内コミュニケーションツールを選ぶ際は、他の業務システムやカレンダー、ファイル共有サービスとの連携機能を確認することも重要です。
ツール間の連携がスムーズだと、情報の一元管理ができ、社員が複数のツールを行き来する手間を減らすことができます。
また、連携機能が充実していると自動通知やデータ同期も可能になり、業務効率の向上やミスの削減につながります。将来的な拡張性も視野に入れて選ぶと安心です。
社内コミュニケーションツール導入時の注意点3選

社内コミュニケーションツールは情報共有や業務効率化に大きな効果を発揮しますが、導入の仕方を誤ると混乱や負担を招く可能性もあります。
したがって、スムーズな活用のためには事前準備と運用ルールが不可欠です。
ここでは、導入前に押さえておくべき3つの注意点を解説します。
マニュアルやルールを整備しておく
ツールを導入する際には、操作マニュアルや運用ルールを事前に整備しておくことが重要です。
ルールがないまま運用を始めてしまうと、情報の散乱や誤送信、その他業務上のトラブルが発生しやすくなります。
こうしたトラブルを防ぐために、たとえばファイル命名規則やチャンネル利用ルール、返信期限などの基本的な運用ルールをあらかじめ定めておくことが大切です。
また作成したマニュアルやルールは社内ポータルや共有フォルダで全社員に周知し、必要に応じて更新していくことで、常に最新の運用体制を維持することができます。
ツール導入の目的を共有しておく
なぜそのツールを導入するのか、目的や期待する効果を全社員に明確に伝えることは、特に初期のオンボーディングにおいて重要です。
なぜならツールの目的が共有されていないと、現場での使い方がバラバラになったり、使用を拒絶する社員が出てきたりして、活用が進まない原因になってしまうからです。
こうした事態を防ぐためにも、たとえば「情報共有のスピードアップ」や「部署間の連携強化」など、具体的なゴールを示すことが有効です。
目的を通じて社員の理解が深まり、積極的な利用が促されます。
また、導入目的を周知する場として説明会や研修を行うと、疑問点を解消しながら統一的な運用が可能になります。
社員のSNS疲れや公私混同に注意する
チャットやSNS型の社内ツールは便利な一方で、通知過多や常時接続によるストレス、私用との混同などのリスクが存在します。
そのため、業務時間外の対応を強制しないルールや、プライベート用と業務用のアカウントを分ける運用を推奨するなどして、社員の負担を軽減する施策も同時に考えていく必要があります。
また、通知設定のカスタマイズや利用マナーの啓蒙を行い、ツールが社員の働きやすさを損なわないよう配慮することが重要です。
適切な線引きが、長期的な活用とモチベーション維持につながります。
社内コミュニケーションツールの効果とメリット4選
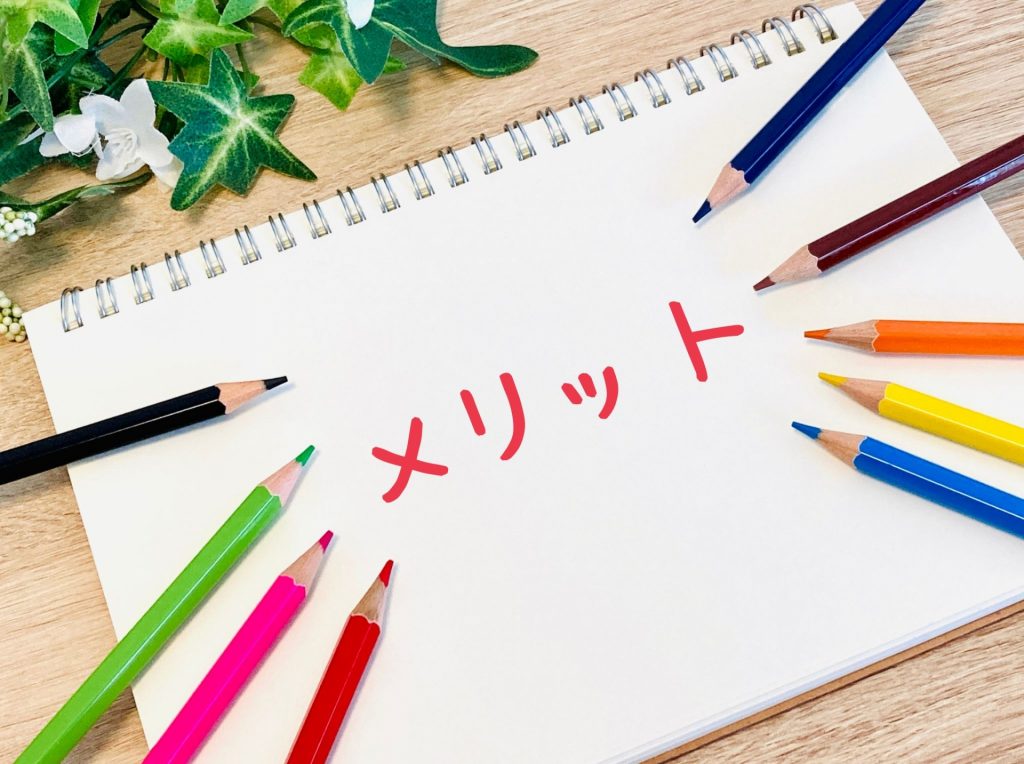
社内コミュニケーションツールは単なる連絡手段に留まらず、業務効率化や組織力の向上にも大きく寄与します。
メールや電話だけでは実現できないスピード感や情報共有の仕組みを提供し、現代の多様な働き方に適応できます。
ここでは、導入によって得られる主な効果とメリットを4つ紹介します。
情報伝達スピードが速い
社内コミュニケーションツールを活用するとリアルタイムでメッセージやファイルをやり取りすることができるようになるため、意思決定のスピードが格段に向上します。
従来のメールは送信・受信・返信に時間がかかり、緊急対応には不向きでした。
しかしチャット機能なら即時のやり取りが可能です。
また、複数人で同時に情報を共有することもできるため、関係者全員が同じタイミングで最新情報を把握できます。
結果として、プロジェクトの進行スピードが上がり、業務の停滞を防ぐことができるのです。
タスクの進捗を把握できる
多くの社内コミュニケーションツールにはタスク管理や進捗共有の機能が備わっています。
これにより、各メンバーの作業状況が可視化され、誰がどの業務を担当しているのか、どこまで進んでいるのかを一目で把握することができるようになります。
特に管理者やチームリーダーにとっては、遅延や課題の早期発見が可能となり、迅速な対応に繋げることができます。
さらに、タスクごとにコメントや資料を紐付けることもできるため、情報の整理もスムーズになり、プロジェクト全体の生産性向上がもたらされます。
社員間のコミュニケーションが活性化する
社内コミュニケーションツールにはチャットや掲示板、スタンプ機能など気軽にやり取りできる機能が充実しているため、社員同士の交流が自然と増えます。
特にリモートワークや拠点間勤務が増えている現代においては、物理的な距離を感じさせないスムーズな連携は組織エンゲージメントの維持・向上に必要不可欠です。
積極的に雑談チャンネルや非公式なやり取りの場を設けることで、チーム内の信頼関係や一体感が高まり、業務のやりやすさにも好影響を与えます。
結果として、社員のモチベーションや定着率の向上につながっていきます。
業務やノウハウの属人化防止に役立つ
社内コミュニケーションツール上で情報やノウハウを共有することで、特定の人だけが知っている業務が減り、属人化のリスクを大幅に軽減することができます。
会議の議事録、業務マニュアル、成功事例などをナレッジとして蓄積すれば、それらは必要な時に誰でもアクセスすることができる強力な情報資源となります。
また検索機能を活用すれば過去のやり取りや資料も簡単に見つけることができるため、新人教育や引き継ぎ作業も効率化します。
結果として、組織全体の知識資産が増え、継続的な業務改善が可能となります。
まとめ|社内コミュニケーションツールの導入でコミュニケーションの活性化や業務効率を向上させよう

社内コミュニケーションツールは、現代の多様な働き方やスピード感のある業務進行に欠かせない存在です。
リアルタイムでの情報共有や迅速な意思決定を可能にし、タスク進捗の可視化やナレッジの蓄積によって業務効率を飛躍的に高めてくれます。
特にリモートワークや拠点間勤務が増える中、距離を超えた円滑な連携や社員間の交流促進は喫緊の課題であることが多いです。
こうした課題を解決してくれるのが、社内コミュニケーションツールであると言えます。
社内コミュニケーションツールを導入する際には、目的を明確にし、自社の業務に合った機能を持つツールを選ぶことが重要です。
また、直感的に使える操作性や他システムとの連携性もチェックポイントとなります。
無料版で実際の業務に適しているかを試し、ルールやマニュアルを整備してから本格運用することで、導入効果を最大化することができます。
一方で、通知過多や公私混同などのデメリットにも配慮が必要です。
業務時間外の対応ルールや利用マナーを明確にし、社員が無理なく活用できる環境を整えましょう。
適切なツール選びと運用ルールの徹底により、社内コミュニケーションは活性化し、組織全体のパフォーマンス向上がもたらされます。
自社に最適なコミュニケーション基盤を整備し、生産性と働きやすさの両立を実現しましょう。
社内コミュニケーションツールに関するよくある質問
Q. 社内コミュニケーションツールの機能は主に何がありますか?
社内コミュニケーションツールには、業務効率化や情報共有を支援する機能が多様に搭載されています。
主な機能は以下の通りです。
- チャット・グループチャット機能
テキストやリアクション・スタンプなどでスピーディかつ直感的なコミュニケーションが可能となります。 - Web会議・ビデオ通話機能
遠隔地どうしの顔を見たやり取りや、画面共有による打ち合わせを実現します。 - ファイル共有機能
ドラッグ&ドロップで簡単に共有でき、最新版の資料を全員が確認することができるようになります。 - タスク管理機能
進捗状況や担当者の可視化により、タスク漏れや遅延を防止することができます。 - ナレッジ共有・社内Wiki機能
マニュアルや知識を蓄積・検索でき、情報の属人化を防ぐことができます。 - 連携機能
グループウェア、カレンダー、業務システムとの連携により、業務を一元化し効率化することができます。
自社にとって必要な機能をリスト化し、ツール比較時の判断基準とすることで、導入後の定着率と効果が大きく向上します。
Q. 社内コミュニケーションツールの費用相場はいくらですか?
社内コミュニケーションツールの費用は導入形態・機能・利用人数などによって幅がありますが、以下に代表的な相場をまとめます。
- 月額従量課金タイプ
1ユーザーあたり500円〜1,500円程度が相場です。無料プランのみ用意するサービスも多く、まずは小規模で試す企業も増えています。 - 初期費用
基本的に無料〜数万円程度ですが、オンプレミス型などでは数十万円以上の導入費用が発生することもあります。 - パッケージ版
たとえば「10ルームまで15万円(初期)」など、ユーザー数やライセンス単位で一括契約する形態も存在します。 - 規模の大きい導入や専門機能付きプラン
月額数十万円〜数百万円規模になるケースもあり、AIなど高度機能付きプランでは初期・月額ともに高額になります。 - Web社内報ツールなどの別カテゴリ
初期0円〜30万円、月額4,000円〜110,000円程度のものもあります。
したがって、最終的な費用は「利用人数」「必要機能」「導入形態(無料・クラウド・オンプレミス)」などによって大きく異なります。
気になるサービスがあれば、問い合わせや見積もりなどで詳細を確認することをお勧めします。
貴社に最適な
ソリューションをご紹介
-
ワンクリックで
クラウドソーシング可能 -
様々な角度から
瞬時にデータ分析 -
フォローのタイミングを
逃さず管理



