おすすめのクレーム管理ツールを紹介!クレーム管理の手順や重要性について解説

日々の業務で発生するクレーム対応に時間や手間がかかり、社内で情報共有や履歴管理の効率化を考えている方も多いでしょう。
特に、対応漏れや二重対応が発生してしまうと、顧客からの信頼を失い、さらに大きな問題に発展するリスクも否定できません。
こうした課題を解決するために、「クレーム管理ツール」の導入を検討する企業が増えています。
そこで本記事では、おすすめのクレーム管理ツールを厳選して紹介するとともに、導入前に押さえておきたい手順や運用ポイント、ツール活用による改善策まで詳しく解説します。
ツール選びや運用方法を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
おすすめのクレーム管理ツール
【第1位】Sales Crowd
・1万社以上にわたる営業支援ノウハウを凝縮
・顧客との会話はすべてAIが自動で文字起こし
【第2位】kintone
・あらかじめ用意されたテンプレートをすぐに導入可能
・対応進捗や発生件数をグラフで可視化できる
【第3位】メールディーラー
・16年連続シェアNo.1、累計8,000社以上が導入
・導入後は専任スタッフのサポートあり
目次
おすすめのクレーム管理ツール6選
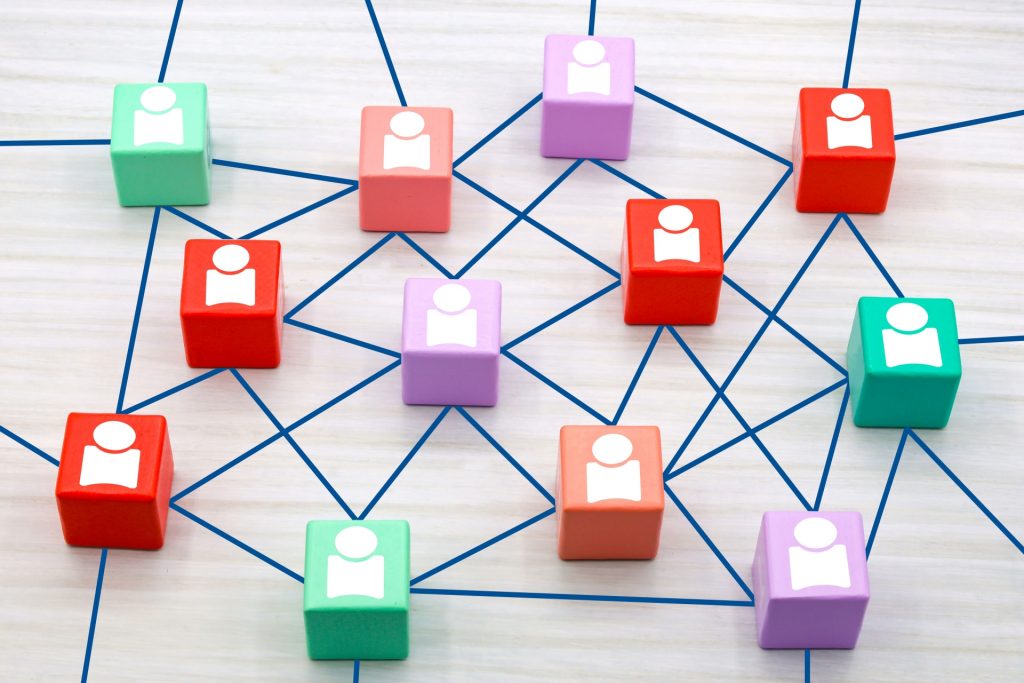
クレーム対応は、顧客満足度を左右する重要なプロセスです。
ここでは、現場で使いやすく、クレーム対応業務を大幅に効率化できるおすすめのクレーム管理ツールを5つ厳選してご紹介します。
各ツールの特徴や強みを比較しながら、自社に最適なツール選びの参考にしてください。
Sales Crowd

Sales Crowdは、1,000万件の独自の顧客データベースと、1万社以上にわたる営業支援ノウハウを凝縮したSaaS型営業支援DXツールです。
これまでの企業の営業支援で蓄積したノウハウを活かして、クレームに対して適切にアプローチします。
顧客との会話はすべてAIが自動で文字起こしするので、クレーム内容を確認して次回以降の営業に活かせます。
また、架電やメールでの営業にも対応していますが、営業に関して高いスキルを有しており、クレームのリスクを抑えた営業が可能です。
営業活動全般の最適化にも強いので、営業プロセス全体を見直したいという方にもぴったりのツールです。
無料デモがあるので、まずは試してみてください。

Sales Crowdの主な機能をご紹介!


あなたに合ったリスト作成だけでなくアプローチ管理にも使える!

\クレームの少ない営業効率が実現/
kintone
サイボウズが提供する「kintone(キントーン)」は、誰でも自社に合わせたシステムを簡単に構築できるクレーム管理ツールです。
サンプルアプリを活用すれば、クレーム内容や対応履歴を一元管理でき、関係者間でスムーズな情報共有が実現します。
特に、クレーム対応に特化した「クレーム管理アプリ」はテンプレートがあらかじめ用意されており、アカウントを作成すればすぐに導入可能です。
さらに、対応進捗や発生件数をグラフで可視化できるので、対応漏れや遅延の防止に効果的。
過去のクレーム対応データも蓄積されるため、新人担当者でも過去事例を参考にしながら適切に対応でき、属人化を防げます。
また、チャットボットやFAQとの連携で初期対応を自動化できるのも強み。結果として、工数削減と顧客満足度の向上を同時に実現できます。
メールディーラー
16年連続シェアNo.1、累計8,000社以上に導入されている「メールディーラー」は、問い合わせメールを一元管理できるクレーム管理ツールです。
複数のアドレスに届くメールをまとめて表示し、対応状況を「未対応」「対応済み」などで可視化。
これにより、対応漏れや二重返信などのミスを防ぎ、チーム全体で質の高い対応を実現します。
さらに、担当者設定や過去履歴の参照、テンプレート機能により、新人でもスムーズに対応可能です。
導入後は専任スタッフのサポートも受けられるため、安心して運用を開始できます。
無料トライアルも用意されており、自社に合った設定や機能を試せるのも魅力です。
Zendesk
「Zendesk」は、世界10万社以上が導入する多機能なカスタマーサービスプラットフォームです。
メールや電話、SNS、チャットなど、さまざまなチャネルからのクレームを一元管理できるのが最大の特徴。
これにより、顧客がどの窓口から連絡してきても、担当者はすべてのやり取りを一つの画面で確認できるため、対応がスムーズに進みます。
さらに、AIが問い合わせ内容を分析し、緊急度の高いものや対応が難しいものを自動で優先順位付けしてくれるため、対応漏れや遅れを未然に防げます。
エンタープライズ向けの分析基盤を備え、部門をまたいだデータ活用で的確な意思決定が可能です。
また、API連携による柔軟なカスタマイズ性も高く、既存システムとの統合運用も容易。
複雑な業務フローを効率化し、顧客満足度と業務効率の両立を目指す企業に最適なクレーム管理ツールです。
yaritori
「yaritori」は、メール対応・顧客管理・一斉配信を一元化できる、シンプルで直感的な操作性が魅力のクレーム管理ツールです。
複数のメールアドレスに届く問い合わせを一つの画面で管理でき、AIがクレームメールを自動検出。
緊急度の高い案件はアラートで通知されるため、迅速な初動対応が可能です。
また、メールごとの対応状況を自由にカスタマイズして可視化でき、担当者間のチャット機能を活用すれば相談や情報共有もスムーズ。
さらに、AI(GPT-4搭載)による返信文作成や自動翻訳、丁寧語変換など高品質な顧客対応をサポートする機能も充実しています。
初めてクレーム管理ツールを導入する企業にも使いやすく、7日間の無料トライアルで手軽に体験できます。
LMIS
「LMIS」は、ITILに準拠したクレーム管理ツールで、問い合わせやインシデントを一元管理できるサービスマネジメントプラットフォームです。
過去の対応履歴やナレッジが自動で蓄積されるため、新人でも類似事例を参考にしながら迅速な対応が可能。
進捗状況の可視化により属人化を防ぎ、チーム全体で対応品質を底上げできます。
さらに、Salesforce基盤のレポート・ダッシュボード機能を活用すれば、クレーム件数や対応時間を多角的に分析し、再発防止策の立案も容易です。
APIや外部システムとの連携機能も備えており、既存の業務フローとの統合もスムーズ。
無期限で使える無料体験版も提供されているため、導入前に操作感をじっくり確認できます。
クレーム管理の手順6つのステップ

クレーム管理を効果的に進めるには、正しい手順を踏むことが重要です。
適切なプロセスを意識することで、対応漏れを防ぎ、顧客満足度の向上につなげられます。
ここからは、クレーム管理の手順を以下6つのステップに分けて詳しく解説していきます。
- 顧客からのクレーム収集
- 分類・整理
- 原因調査と対応方針の決定
- 顧客対応と結果報告
- 対応履歴の記録管理
- 検証と改善
1. 顧客からのクレームを収集する
クレーム管理の第一歩は、顧客からの声を正確かつ迅速に収集することです。
初動で情報を取りこぼすと、対応遅延や顧客不満の拡大につながります。
電話・メール・チャット・SNSなど、複数の窓口から寄せられるクレームを一元的に管理できる仕組みを整えることがポイントです。
クレーム管理ツールを活用すれば、問い合わせを自動で記録し、誰が見ても状況を把握しやすくなります。
情報を正しく収集することは、迅速かつ適切な対応の基盤を築くために欠かせません。
2. 内容に応じてクレームを分類・整理
収集したクレームは、内容や緊急度に応じて分類・整理することが重要です。
分類が曖昧なままだと、優先度の高い案件への対応が遅れ、顧客満足度を下げるリスクがあります。
クレーム管理ツールを使えば、「未対応」「対応中」「完了」などのステータス管理が簡単にでき、担当者の割り当てもスムーズです。
さらに、原因や対応履歴を紐づけて管理することで、同様のクレームが発生した際にも素早く対応可能。
情報を整理することで、チーム全体の業務効率と対応品質を同時に高められます。
3. 原因調査と対応方針の決定
適切なクレーム対応には、原因調査と対応方針の明確化が欠かせません。
問題の根本原因を正しく把握できなければ、再発を防げず、同様のクレームが繰り返される可能性があります。
このステップでは、当事者や関係者から詳細なヒアリングを行い、客観的な事実に基づき原因を徹底的に調査しましょう。
その上で、「顧客満足度」「コスト・リスク」「客観的データ」などを多角的に評価し、最も適切な対応方針を決定します。
クレーム管理ツールに過去の類似案件や解決策がナレッジとして蓄積されていれば、スムーズに原因調査や対応方針を立てられるでしょう。
正確な原因特定と計画的な対応が、顧客との信頼関係を築く近道です。
4. 顧客への対応と結果報告
クレーム対応では、「スピード」と「誠意」が何よりも重要です。
対応が遅れたり、報告が不透明だと、顧客の不信感を招き、さらなるクレームに発展する可能性もあります。
対応にあたる担当者は、進捗状況をリアルタイムでクレーム管理ツールに記録・共有し、チーム全体で状況を把握することが重要です。
クレームが解決した後は、その結果を顧客に丁寧に報告しましょう。
この際、単に「解決しました」と伝えるだけでなく、原因や今後の再発防止策についても説明することで、顧客との信頼がより深まります。
クレーム管理ツールを使えば、進捗管理や報告書作成も効率化され、複数担当者間で情報を統一できるため、チーム全体で一貫した対応が可能です。
5. 対応履歴の文書化・記録管理
クレーム対応が終わったら、その対応履歴を詳細に文書化し、記録として管理しましょう。
詳細な記録を残すことで、再発防止策の立案や対応方針の見直しに役立ちます。
さらに、ツールを活用してデータを一元管理すれば、過去事例をすぐに検索でき、新人教育や社内共有にも効果的です。
対応内容をチーム全体で共有することで、業務の属人化を防ぎ、誰でも同じ水準の対応が可能になります。
記録を残すことは、長期的なクレーム管理体制の強化に直結します。
6. 対応内容を検証し改善に活かす
最後のステップは、対応内容を検証し、組織全体の改善に活かすことです。
対応して終わりにしてしまうと、同じ問題が繰り返し発生するリスクが高まります。
クレーム管理ツールに蓄積された対応履歴を分析し、「どのような種類のクレームが多いのか」「特定の製品やサービスに集中していないか」といった傾向を明確にしましょう。
これらのデータを基に、製品やサービスそのものの改善、業務プロセスの見直し、マニュアルの修正など、具体的な改善策を立てて実行することで、クレームの発生件数を根本的に減らすことが可能になります。
顧客からのクレームは、企業が成長するための重要なヒントと捉えましょう。
クレーム管理の重要性

クレーム管理は、単に苦情を処理するためだけの業務ではありません。
クレームは、時に顧客からの貴重なフィードバックであり、サービスや製品を改善するための重要な役割を担っています。
ここでは、なぜクレーム管理が重要なのか、その5つの理由を掘り下げていきましょう。
ツール導入前にその重要性を理解し、自社サービスの品質向上にお役立てください。
現状把握と課題の可視化
クレーム管理の効果を最大化するには、現状を正確に把握し、課題を可視化することが欠かせません。
クレーム対応を個別に行うだけでは、全体の傾向や根本的な問題を見過ごしてしまいがちです。
詳細なクレーム情報を集約して共有すれば、対応漏れや重複を防ぎ、業務の効率化につながります。
また、クレーム管理ツールを活用してクレームの内容や進捗状況を可視化することで、緊急性の高い案件から優先的に対応できる体制を構築できます。
これにより、組織全体の課題が浮き彫りになり、サービスの品質向上や顧客満足度の継続的な改善へとつなげられるでしょう。
クレーム対応の知見を蓄積
クレーム管理は、クレーム対応の知見を組織全体に蓄積し、対応力の向上と再発防止に貢献します。
クレーム対応が属人化していると、担当者の異動や退職によってノウハウが失われるリスクが生じます。
クレーム管理ツールを活用すれば、すべての履歴をオンラインで一元管理でき、担当者間で情報を共有しやすくなります。
蓄積したデータを分析すれば、再発防止策や改善施策の立案が効率化。
さらに、ナレッジベース化することで新人教育にも役立ち、誰でも過去の成功事例を参考に迅速な対応が可能になります。
これにより、チーム全体の対応品質を底上げできるでしょう。
対応手順の統一化
クレーム対応の質を均一化し、効率を向上させるためには、対応手順を統一させることが不可欠です。
担当者によって対応方法が異なると、顧客に不公平感を与えてしまい、さらなる不満につながる可能性があります。
その点、クレーム管理ツールを活用して標準化したマニュアルやナレッジを共有すれば、全員が同じ基準で対応可能です。
これにより、対応のばらつきを防ぎ、常に迅速かつ適切な対応を実現。
また、対応手順が明確になることで、担当者の精神的な負担を軽減し、より前向きに業務に取り組むことができるようになります。
組織全体で対応品質を均一化できるため、顧客からの信頼も高まりやすくなるでしょう。
対応漏れ・二重対応の防止
クレーム管理において、対応漏れや二重対応を防ぐ仕組みづくりは欠かせません。
複数の担当者が個別にクレーム対応を行っていると、互いの進捗状況が分からずに対応が遅れたり、顧客に同じ内容の返信を繰り返してしまうといったトラブルが発生しやすいです。
クレーム管理ツールを使えば、すべての問い合わせ内容と対応進捗を一元管理し、担当者間の連携ミスを大幅に削減します。
さらに、AIによる自動振り分け機能や履歴共有機能を活用すれば、誰でも現在の対応状況を把握できるため、未処理やダブル対応を最小限に抑えられます。
これにより、顧客からの信頼を損なうことなく、スムーズなコミュニケーションを実現できるでしょう。
新たな改善策やサービス向上への活用
クレーム管理は、顧客の不満を解消するだけでなく、サービス品質を向上させるための重要な機会です。
単にクレームを処理するだけでなく、その背景にある根本原因を分析し、改善策に活かすことが重要になります。
クレーム管理ツールに蓄積された膨大なデータを分析することで、「製品やサービスのどの部分に課題があるのか」「どのようなクレームが多いのか」といった傾向を把握できます。
さらに、AIがクレーム内容や感情分析で課題を検出することで、顧客の不満度やリスクを早期に検知可能です。
これらのデータを基に、全社的な改善施策を立案し、サービス品質の向上に直結させられます。
クレームを”活かす仕組み”を整えることが、顧客満足度の向上と継続的なビジネス成長を促す原動力となるでしょう。
クレーム管理ツールを運用する際のポイント

クレーム管理ツールを効果的に活用するには、単に導入するだけでなく、運用時の工夫が重要です。
運用方法を誤ると、かえって業務が煩雑になったり、対応ミスを招いてしまう可能性もあります。
ここでは、クレーム管理ツールを最大限に活用し、顧客満足度と業務効率を同時に向上させるための重要なポイントを3つご紹介します。
正確で漏れのない情報共有を徹底する
クレーム管理ツールを効果的に運用するには、正確かつ漏れのない情報共有を徹底することが欠かせません。
情報が不正確だったり、共有に抜けがあると、担当者間の認識にズレが生じ、結果として対応の遅延や二重対応につながる恐れがあります。
最新のクレーム管理ツールは、AIがクレームの内容を自動検出し、ステータスや対応履歴をリアルタイムで共有する機能が備わっているものも多いです。
これにより、すべての関係者が常に最新の情報を把握でき、誰がどのクレームに対応しているのかが一目でわかります。
組織全体で共通の情報を参照することで、無駄なやり取りをなくし、迅速で一貫性のある顧客対応が可能になります。
対応進捗をリアルタイムで共有する
対応状況のリアルタイム共有は、情報連携を円滑にし、クレーム対応の漏れを防ぐために欠かせない要素です。
進捗状況が不明瞭だと、担当者が「対応完了」と認識していても、実際には未対応のまま放置されてしまうことも起こり得ます。
多くのクレーム管理ツールでは、クレームの進捗を「未対応」「対応中」といったステータスで即座に更新・共有が可能です。
さらに、AIがクレーム内容を分析し、緊急度を自動判定して通知する機能を組み合わせることで、優先度の高い案件をスピーディーに処理できるようになります。
リアルタイムで進捗状況を把握できる体制を整えることで、対応漏れを最小限に抑えつつ、迅速で的確なクレーム対応を実現できるでしょう。
顧客情報・個人情報を適切に管理する
クレーム管理ツールの運用において、顧客情報や個人情報を適切に管理することは、企業の信頼性を守る上で最重要課題です。
クレーム対応では、顧客の名前・連絡先・購入履歴など、機密性の高い情報を扱うことが多いため、情報漏洩のリスクを常に意識しなければなりません。
個人情報保護法などの法令を遵守することはもちろん、情報漏洩を防ぐための強固なセキュリティ対策が求められます。
多くのクレーム管理ツールには、アクセス権限の設定やログ管理、データの暗号化といったセキュリティ機能が実装されています。
これらの機能を活用し、「誰が、いつ、どのような情報にアクセスしたか」を厳格に管理することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
また、クラウド型ツールを導入すれば、社内外を問わず安全な環境で情報を扱えるため、効率性とセキュリティの両立が可能になります。
まとめ|クレーム管理ツールの導入で顧客対応の質向上と業務効率の両立を実現
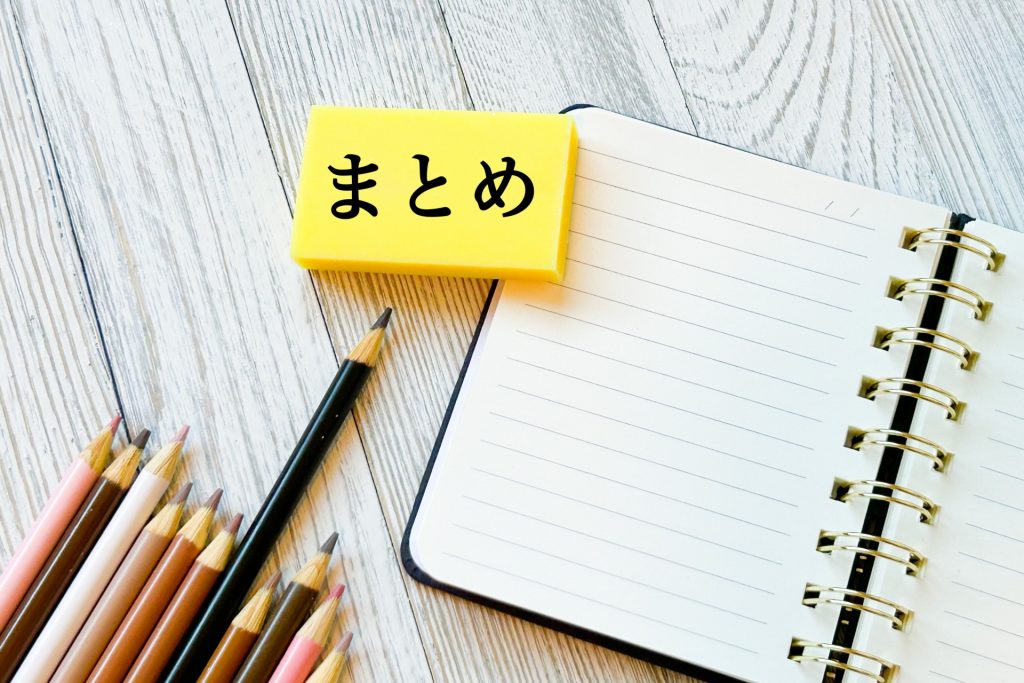
クレーム管理ツールは、顧客対応の質を高めながら、社内業務の効率化も同時に実現できる強力な手段です。
ツールを使えば、クレーム情報の一元管理や対応履歴の記録、進捗状況の可視化が可能になり、担当者ごとの対応のばらつきを抑えつつ、迅速な処理が行えます。
さらに、過去の対応データやナレッジを蓄積・分析すれば、再発防止策や改善策の立案も効率化され、サービス品質向上にもつながります。
導入時は、機能性や操作性・セキュリティ・コスト面を自社の運用方針や規模に照らして慎重に選ぶことが大切です。
適切なツールを選び、組織全体で活用することで、顧客満足度の向上と業務効率の両立、さらに改善文化の定着まで期待できるでしょう。
とはいえ、クレームはないに越したことはありません。
Sales Crowdなら、適切なタイミング・内容でアプローチができるため、不要な架電や一方的な営業を減らせます。
人の勘に頼らない営業により、相手に配慮したコミュニケーションを実現できるのが強みです。
結果として、クレームリスクを抑えながら、効率的で質の高い新規開拓につながります。
\顧客が納得できる営業をする/
クレーム管理ツールに関するよくある質問
-
クレーム管理ツールの導入コストはどのくらいかかりますか?
-
クレーム管理ツールの導入コストは、利用するツールの種類や機能、契約形態によって大きく異なります。
初期費用や月額料金が比較的安価な「クラウド型」のツールであれば、月額数千円から利用も可能です。
一方で、自社サーバーに構築する「オンプレミス型」のツールでは、初期費用だけで数十万円規模の費用が発生することもあります。
まずは、自社の企業規模や最低限必要な機能をリストアップし、それに合った料金体系のツールを比較検討することをおすすめします。
多くのツールでは無料トライアルが用意されているため、実際に試してみるのも良いでしょう。
-
セキュリティや個人情報保護は大丈夫ですか?
-
多くのクラウド型クレーム管理ツールは、強固なセキュリティ機能を備えています。
具体的には、「データの暗号化」「IPアドレスによるアクセス制限」「ユーザーごとのアクセス権限設定」「操作履歴のログ管理」といった対策が講じられていることが多いです。
これらの機能により、情報漏洩や不正アクセスを防止し、安心して情報を管理できます。
ツールのセキュリティ対策だけに頼るのではなく、自社の情報管理ポリシーや法令遵守の基準と照らし合わせて導入を検討しましょう。
適切な情報管理を徹底することで、顧客との信頼関係を維持し、企業の信用を守れます。
-
クレーム管理はエクセルではだめですか?
-
問題ないですが、件数が増えると管理が煩雑になりやすく、抜け漏れや対応遅れが起こるリスクがあります。
担当者ごとの対応状況や履歴をリアルタイムで共有しづらい点も課題です。
一方、管理ツールを使えば、対応状況の可視化や履歴の一元管理などができます。
結果として対応品質が安定し、クレームの再発防止や顧客満足度の向上につながるため、長期的にはツール導入のほうが効率的です。
貴社に最適な
ソリューションをご紹介
-
ワンクリックで
クラウドソーシング可能 -
様々な角度から
瞬時にデータ分析 -
フォローのタイミングを
逃さず管理



