おすすめの営業分析ツールを紹介!営業分析の必要性や手法について解説

近年のビジネス環境は変化のスピードが速く、従来の経験や勘に頼った営業活動では成果を出し続けることが難しくなっています。
顧客のニーズは多様化し、競合も次々と新しい手法を取り入れるなかで、営業現場には「より効率的に成果をあげる仕組みづくり」が求められています。
こうした背景から、いま注目を集めているのが営業分析ツール です。
営業分析ツールでは、商談件数や成約率、通話ログや訪問履歴といった膨大なデータを整理し、数値に基づいた改善ポイントを可視化することができるため、属人化しやすい営業活動を組織的に強化することが可能になります。
しかし実際には、「どのツールを選ぶべきか」「導入後に使いこなせるのか」といった不安を抱える担当者も少なくありません。
効率的にデータを管理・分析したい、チームの成約率を高めたいと考えていても、比較検討や活用のイメージがつかめず、導入をためらうケースも多いのです。
そこで本記事では、営業分析ツールの基本的な役割や導入メリットを整理し、活用のヒントやおすすめサービスを紹介します。
営業活動の質を高め、売上向上へとつなげたい経営者やマネージャー、現場社員の方はぜひ参考にし、自社の営業推進に役立ててください。
目次
おすすめの営業分析ツール

営業成果を最大化するためには、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた戦略的な意思決定が欠かせません。
しかし、実際の現場では「データを収集しても活用できていない」「そもそも何から手をつけたらいいのかわからない」といった悩みが多く散見されます。
そんな中、注目されているのが営業分析ツール です。
営業活動で得られる顧客情報や案件データ、通話履歴、行動ログを一元管理し、分析・可視化してくれる営業分析ツールは、個々の営業担当のパフォーマンスを引き上げ、組織全体の成果を引き上げることに役立ちます。
本章では、特に評価の高い4つの営業分析ツールをピックアップし、それぞれの特徴や強みを詳しく紹介していきます。
ツールの導入を検討している担当者やマネージャーの方は、ぜひ検討材料としてご活用ください。
Sales Crowd(SFA)
Sales Crowdは、国内最大級の企業データベースを基盤とした営業分析ツールです。
MA・SFA・CRMの機能を一体化して提供していることから、従来は複数ツールを組み合わせる必要があった「顧客管理」「メール配信」「架電管理」などをワンストップで実現できることに特徴があります。
特に注目すべきは、リスト作成から架電・メール送信までをワンクリックで実行できる利便性にあります。
こうした機能を活用することで、営業担当者は本来のコア業務である「商談」に集中する環境を整えることができます。
さらに、Sales Crowdは直感的に操作できるUI設計を採用しているため、システムに不慣れな担当者でもスムーズに利用を開始できます。
企業データベースを活用したターゲティング機能は、アプローチの質を高めるだけでなく、無駄な営業活動を減らす効果も期待できます。
効率化と成果創出を同時に実現したい企業にとって、Sales Crowdは導入を検討する価値の高い営業支援ツールであると言えます。
料金体系はプランの内容によって変わってきますが、ミニマムの利用は月額10万円からとなっています。詳細は問い合わせをして確認しましょう。
Mazrica Sales(SFA)
Mazrica Salesは、AIを搭載した国産の営業分析ツール(SFA/CRM)です。
営業活動の精度を高める仕組みを豊富に備えており、過去の成功・失敗事例を学習し、「いつ」「誰に」「何を」アクションすべきかを自動で提案してくれる点に大きな強みを持っています。
さらに、営業やCS(カスタマーサクセス)の活動履歴を蓄積し、組織知として活用できる機能も搭載しているため、部門横断的な価値創出を実現してくれます。
案件管理は直感的なUIで操作できるため、進捗の見える化と行動の最適化を同時に実現することが可能です。
小規模チームでも導入しやすい月額5,500円〜のプランが用意されており、豊富な導入事例や高いサポート評価も安心材料です。
AIとデータを組み合わせて営業力を底上げしたい企業にとって、Mazrica Salesは心強い選択肢となってくれるでしょう。
料金体系は、1ID5,500円〜/月のStarterプラン(最低月額料金:27,500円)、1ID11,000円〜/月のGrowthプラン(最低月額料金:110,000円)、1ID16,500円〜/月のEnterpriseプラン(最低月額料金:330,000円)が存在します。
AI活用やカスタム性がグレードアップするにつれて豊富になるため、自社の営業方針に即したプランを選択すると良いでしょう。
LaKeel BI(BIツール)
LaKeel BIは、データの統合から可視化・分析までを一貫して行うことができる国産のBIツールです。
営業活動におけるデータは社内の各システムに分散しがちですが、LaKeel BIを導入すればそれらを一元的に統合することができ、全社的な情報共有と迅速な意思決定が可能となります。
豊富なテンプレートが用意されており、Excelとの親和性も高いため、分析ツールに不慣れなユーザーでも導入しやすい点が魅力です。
さらに注目すべきなのは、生成AIを活用した「LaKeel BI Concierge」機能でしょう。
自然言語で質問するとAIがデータを解析し、洞察を返してくれるため、専門知識がなくても高度なインサイトを得ることができます。
営業チームが直感的にデータを活用できるようになることで、分析に費やす時間が削減され、本来の戦略立案や顧客対応に集中できるようになります。
営業活動の効率化だけでなく、経営判断の高度化にも役立つツールであると言えます。
料金体系は、サーバーライセンス型の価格体系となっており、データ量やユーザー数増加による追加コストの心配なく利用することが可能です。実際の価格については、問い合わせをして確認しましょう。
>>LaKeel BIに問い合わせる
Tableau(BIツール)
Tableauは、世界的に利用されているBIツールであり、直感的なドラッグ&ドロップ操作によって誰でも簡単にデータを可視化できます。
プログラミングや高度な分析スキルを必要とせず美しいグラフやダッシュボードを作成することができるため、低労力で視覚的に理解しやすい営業データを得ることができます。
さらに、クラウドやオンプレミスなど接続先が非常に豊富であるため、既存のデータ基盤を活かした導入が可能となっています。
小規模なデータ活用から大規模な企業全体の分析基盤まで幅広く対応できる拡張性の高さは、他のツールにはない大きな魅力であると言えるでしょう。
また、Tableauはユーザーコミュニティも活発であり、活用ノウハウが豊富に共有されています。そのため、導入後の定着化を支援する環境も整っていると言えます。
営業データの見える化を強力に推進し、チーム全体の意思決定スピードを高めたい企業にとって、Tableauは非常に有力な営業分析ツールといえるでしょう。
料金体系は下記のようになっています。
【Tableau Plan】
- Tableau Viewer:1ユーザー1,800円/月
- Tableau Explorer:1ユーザー5,040円/月
- Tableau Creator:1ユーザー9,000円/月
【Enterprise Plan】
- Enterprise Viewer:1ユーザー4,200円/月
- Enterprise Explorer:1ユーザー8,400円/月
- Enterprise Creator:1ユーザー13,800円/月
【Tableau+ Plan】
要問い合わせ
詳しくは問い合わせをし、自社の課題と用意されているプラン内容をすり合わせましょう。
営業分析ツールが必要な理由
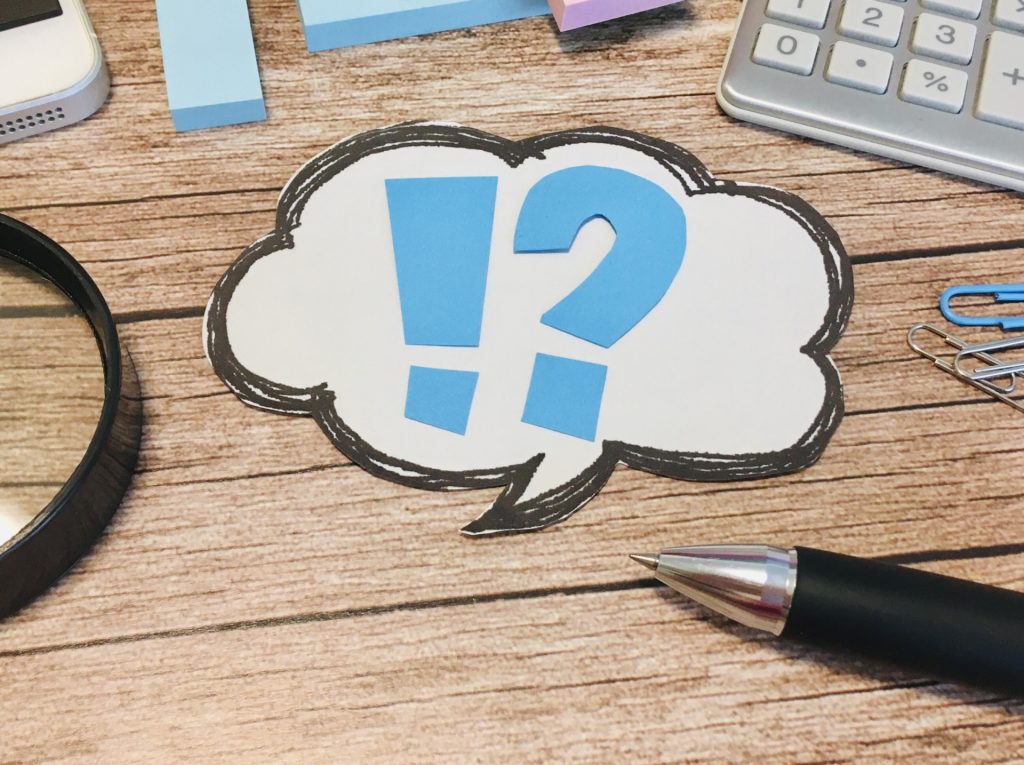
現代の営業活動は、顧客との接点が多様化し、データ量も飛躍的に増加しています。
しかし、蓄積されたデータを十分に活かすことができず、属人的な営業に依存してしまっている企業も決して少なくありません。
その結果、営業戦略が個人任せとなり、成果にばらつきが出たり、売上予測や改善の精度が低下するリスクが生じています。
こうした課題を解決するために注目されているのが「営業分析ツール」です。
ここでは、企業にとって営業分析ツールが必要となる理由を、要点に絞って解説していきます。
ノウハウや営業戦略の共有
営業分析ツールを導入する大きな理由のひとつが、ノウハウや営業戦略の共有です。
営業活動を可視化することで、各担当者の進捗や課題を把握しやすくなり、成功事例だけでなく失敗事例も含めた分析が可能になります。
これにより、属人的だった営業プロセスを標準化でき、改善ポイントを具体的に明確化することができます。
特に新人教育の場面では、実際の事例をもとに「どのように話せばアポイントが取れるか」「失注した案件のどこに課題があったのか」といった具体的な指導が可能になります。
経験豊富な営業担当者のノウハウを組織全体に共有することができるため、人材育成のスピードも向上し、結果として営業チーム全体のスキルの底上げにつながります。
正確な売上予測
営業分析ツールのもう一つのメリットは、売上予測の精度を高められることです。
ツールを用いて営業データを可視化すると、目標と現状のギャップをリアルタイムで把握することができるようになり、戦略の見直しやリソース配分をスピーディーに行うことにつながります。
また、エリア別や担当者別に分析をすることで、売上が低迷している要因を明確化することができ、「どの地域でアプローチを強化すべきか」「どの担当者にサポートが必要か」といった具体的なアクションに落とし込むこともできるようになります。
さらに、正確な売上予測は市場変化への迅速な対応にも役立ちます。
競合の動向や需要の変化に先回りして施策を打つことで、ビジネスリスクを軽減しつつ、安定した成長を支えることができます。
営業分析ツールは単なる業務効率化の手段にとどまらず、未来の売上を見据えた経営の羅針盤的な存在となり得るのです。
属人化の防止
営業分析ツールを導入すると活動内容や成果をデータとして蓄積・可視化できるようになるため、個人に依存した営業手法から脱却しやすくなります。
たとえば、成功事例や失敗事例を共有する仕組みを整えることで、特定のトップセールスだけが成果を出すのではなく、組織全体が同じレベルで実行できる体制を構築できます。
また、営業プロセスの標準化が進むことで、新人教育や引き継ぎもスムーズになり、人材の入れ替わりによる業績低下のリスクを大幅に軽減できます。
属人化を防止することは、組織の安定した成長に必要不可欠です。
この際、営業分析ツールは、営業活動を「個人のスキル」から「組織の資産」へと昇華させる役割を担い、持続的な成果創出につなげる役割を果たしてくれます。
顧客ニーズへの対応
営業分析ツールを活用すれば、顧客の購買傾向や過去のやり取り、関心の高い商品をデータで把握することができるようになり、ニーズの変化を早期に察知することが可能となります。
例えば、ある顧客が過去に購入した製品の利用状況や問い合わせ内容を分析すれば、次に必要とされるサービスを先回りして提案することが可能となります。
このように、データに基づきながら戦略的に顧客満足度の向上やリピート率の強化を実現することが、営業分析ツールを通じて可能となります。
また、市場動向や競合他社の動きを踏まえた上で、顧客に最適な提案をスピーディーに行うことは、競争優位性を確立することにもつながります。
営業分析ツールは、顧客理解を深め、関係性を強化するための強力な武器となり得るのです。
営業分析の手法

営業成果を高めるためには、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた「営業分析」が必要不可欠です。
営業分析にはさまざまな手法があり、それぞれ目的や活用シーンが異なります。市場全体を俯瞰する分析から、顧客ごとの購買行動を掘り下げるもの、さらには営業活動の過程を可視化するものまで多岐にわたります。
ここでは代表的な営業分析手法を紹介し、それぞれの特徴やメリットを解説していきます。
動的分析
動的分析は、業界や自社の売上推移、市場動向をグラフ化して可視化することで、自社の立ち位置を把握する手法です。
競合との売上比較やトレンド把握を行うことで、「市場全体が伸びているのに自社だけが停滞している」「ある製品カテゴリーが急成長している」といった気づきを得やすく、新たなビジネスチャンスを発見するのに役立ちます。
動的分析は全体像を掴むのに優れている一方で、詳細な要因分析には不向きなため、他の分析手法と組み合わせて活用することが効果的です。
経営層に向けた報告資料や戦略立案の初期段階でよく用いられる、基礎的なアプローチであると言えます。
要因分析
要因分析は、動的分析で得られた売上や市場変化に対し、「なぜそうなったのか」という原因を探る手法です。
ここでは例えば、競合が急成長している場合、その背景にあるのはSNS広告なのか、テレビCMなのか、あるいはキャンペーン施策なのかといった風に推測・分析していきます。
この分析によって自社の戦略に活かせるヒントを得ることはできますが、その結果はあくまで仮説に過ぎません。
実際に有効かどうかを確認するには、次のステップである検証分析が必要となります。
つまり、要因分析は「問いを立てる」段階であり、的確な仮説を導き出せるかどうかが分析の巧拙を決定します。
検証分析
検証分析は、動的分析や要因分析で立てた仮説をデータ収集やテストによって確認する手法です。
例えば、SNS広告が売上増加の要因だと仮定した場合、実際に広告配信を強化し得られた結果を比較することで、その真偽を裏付けることができます。
こうした検証によって効果の高い施策が特定され、結果としてリソース配分の最適化が可能となります。
さらに、成果の出ない施策についても改善ポイントを明確化することができるため、施策の最適化にもつながります。
ただし、この分析は仮説が曖昧なまま実施しても十分な結果を得ることができません。
事前準備と目的の明確化こそが、検証分析成功の前提条件となります。
KPI分析
KPI分析は、営業活動の達成度を数値で測るために重要業績評価指標(KPI)を設定し、分析する手法です。
具体的には「アポイント数」「商談件数」「クロージング件数」などをKPIとして設定し、歩留まりごとに状況を分析します。
これによって、トップセールスと他メンバーの差分や改善ポイントがどこにあるのかを明確に把握することができます。
差が出ている要素を特定することで、重点的な改善に取り組み、営業パフォーマンス全体の向上につなげることが可能となります。
行動分析
行動分析は、営業担当者の行動データを調査し、成果の違いを明らかにする手法です。
架電数や訪問数、メール送信数といった行動指標を分析し、成果を出す人と出せない人の差を浮き彫りにします。
例えば、成績上位者が平均より多くの訪問を行っているなら、その行動を標準化し、他のメンバーに展開することでチーム全体の成果向上が期待できます。
行動分析は単なる数量把握ではなく、行動と成果の関係を紐解くことに意味があります。
成功パターンを共有し、組織全体の営業力を底上げするための有効なアプローチであると言えます。
顧客分析
顧客分析は、顧客の属性や購買履歴をもとにニーズを精緻に把握することで、売上アップにつなげる手法です。
購買データや問い合わせ履歴を分析することで、「どの商品に興味があるのか」「どのタイミングで購入しやすいのか」といったインサイトを得ることができます。
これにより、顧客に合った商品・サービスの改善や新商品の開発が可能となり、顧客満足度の向上につながっていきます。
また、購買パターンからリピーター向けのキャンペーンを設計することで、効果的な集客と売上拡大を実現することもできます。
このように、顧客分析は顧客理解を深めるための基盤となる分析手法であると言えます。
商談分析
商談分析は、商談内容や提案手法を振り返り、商談の質を高めるための分析手法です。
成功した商談と失敗した商談を比較し、「顧客の属性に合わせた提案ができていたか」「トーク内容は適切だったか」といった要因を評価することで、改善すべき具体的なポイントを明らかにします。
また、成功事例を共有することはチーム全体の商談力も高め、組織的な成果向上につながっていきます。
このように商談分析は単なる数値管理ではなく、質の改善に焦点を当てる点が特徴的です。
競合分析
競合分析は、自社と競合の製品・サービス、戦略の違いを把握するための手法です。
3C分析や4P分析、SWOT分析などのフレームワークを活用し、多角的に評価していくことで、自社が強みを活かせる領域や競合の弱みを突けるポイントを明確化します。
例えば、競合が低価格戦略を取っている場合、自社は品質やサポート面で差別化を図るといったように、競合を深く理解し自社の立ち位置を再確認することは、新たな市場参入や戦略転換の判断材料となります。
営業パイプライン分析
営業パイプライン分析は、問い合わせから成約に至るまでの営業プロセス全体を可視化する手法です。
問い合わせ、ヒアリング、提案、見積もり、成約といった各段階を定量的に分析し、どこにボトルネックがあるのかを明確にします。
例えば、提案までは順調でも見積もり以降で失注が多い場合、価格提示や条件交渉に課題があると判断できます。
この分析は営業活動を分解して捉えることを可能にするため、プロセス改善や売上予測の精度向上、組織的な営業力強化につながります。
コホート分析
コホート分析は、特定の条件で顧客をグループ化し、世代別や属性別に消費行動を比較する手法です。
例えば、セミナー参加者とWeb広告経由の見込み客をグループ化して成約率を比較すれば、どの施策が高い効果をもたらすかが明らかになります。
これにより、営業予算の効率的な配分や施策の優先順位付けが可能になります。
また、顧客の行動パターンを深掘りすることで、ターゲティング精度が向上し、効果的な戦略立案にもつながります。
ABC分析
ABC分析は、売上やコスト・在庫を基にA・B・Cに分類し、優先度を明確にする手法です。
パレートの法則に基づき、売上の大部分を生み出す主力商品を「A」として重点管理し、利益が少ない商品を「C」として在庫削減や撤退を検討します。
例えば、売れ筋商品を特定してAに分類し、在庫を切らさないよう管理することで機会損失を防止するといったように、在庫管理や商品戦略の基本として広く用いられています。
SWOT分析
SWOT分析は、自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を4象限で整理する手法です。
内部と外部の要因を体系的に把握することで、適切な戦略や意思決定が可能になります。
例えば、自社の「技術力」という強みと「新興市場」という機会を組み合わせれば積極的な参入戦略を立案できます。
一方で「高コスト」という弱みと「価格競争」という脅威が重なる場合は撤退を検討する必要があります。
このようにSWOT分析は、戦略立案の基本フレームワークとして幅広く活用されています。
営業分析ツールで注目したい重要な指標

営業分析ツールを利用する際に、適切な指標を設定・分析することは成功の鍵を握る重要事項です。
ここでは、営業分析ツールを用いる際に注目したい重要な指標を、5つピックアップしてご紹介します。
新規リード
新規リードとは、新たに獲得した見込み顧客(営業対象候補)のことを指す、営業活動の出発点となる重要な指標です。
新規リードを追う際にポイントとなるのは、リードの「数」だけでなく「質」に注目することです。
例えば、展示会で得た名刺情報やWeb広告からの問い合わせはいずれもリードとして管理されることになりますが、すべてが同じ成約率を持っているとは限りません。
このように、質の異なるリードが大量に得られた場合でも、営業分析ツールを活用すれば、流入経路や属性に基づいてリードを定量的にスコアリング(成約の確度決め)することができ、有望な顧客へのアプローチを強化できます。
質の高い新規リードを安定的に獲得することは、売上の拡大や営業活動の最適化に直結する重要事項です。そのため、新規リードの様態は注視し数値を追っていく必要があります。
CVR
CVR(コンバージョン率)は、訪問者数に対して実際に成果に至った割合を示す指標のことです。
例えば、Web広告経由で1000人の訪問者を集め、そのうち50人が購入や問い合わせにつながった場合、CVRは5%となります。
CVRは、営業やマーケティング活動の効率性や効果性を測定するうえで欠かせない要素であると言え、改善すべきポイントを明確にする役割を果たします。
例えばCVRを比較することで各広告の内容や営業トークの改善余地の把握、あるいはターゲット設定や導線設計の見直しへとつなげていくのです。
成約見込み案件
成約見込み案件とは、商談が進展し成約に至る可能性が高いと判断された案件のことを指します。
例えば、価格交渉が進行中の案件や、顧客が見積もり承認を検討している段階の案件は、成約見込み案件として分類できます。
この際、営業分析ツールを活用すれば、案件ごとの進捗や成約確率を明確かつ簡易に把握することが可能となります。
成約見込み案件を正しく捉えることは、フォローすべき顧客を正しく選定し、効果のあるリソース配分を実現する鍵となるのです。
平均取引額
平均取引額は、一定期間における総売上を取引件数で割った金額のことで、営業活動の収益性を測る基本的な指標です。
例えば、月間売上が1000万円で取引件数が200件の場合、平均取引額は5万円となります。
この指標を把握することで、自社のビジネスモデルや顧客単価の傾向を理解することができ、今後の営業戦略や予算計画の立案に役立ちます。
また、顧客ごとの平均取引額を分析すれば、クロスセルやアップセルの余地を見つけることも可能です。
営業分析ツールを導入すれば、商品カテゴリ別や顧客属性別に平均取引額を可視化することができ、重点強化すべき領域が明確になります。
効率的な売上拡大を目指すためには、平均取引額の変動を継続的に追跡し、改善施策に活かすことが必要不可欠です。
セールスサイクル
セールスサイクルとは、新規リードの獲得から成約、アフターフォローに至るまでの営業プロセス全体のことを指します。
このサイクルの長さや流れを把握することで、営業活動の効率化やボトルネックの特定が可能になります。
営業分析ツールを使えば、アプローチ・商談・交渉・見積もりといった各プロセスを可視化し、進捗率や滞留期間を定量的に把握することが可能となります。
さらに、KPIを設定して改善を進めれば、成約スピードを高め、売上予測の精度も向上します。
セールスサイクルを分析することは、営業チーム全体の生産性を引き上げる基盤づくりにつながります。
まとめ|営業分析ツールは規模と目的で選ぼう

営業分析ツールを効果的に活用するためには、単にデータを蓄積するだけでなく、成果につながる指標を正しく把握・分析することが重要です。
先述した指標等を組み合わせて分析することで、営業活動の属人化を防ぎ、組織全体のナレッジ共有や意思決定のスピード向上につなげるのです。
ツールを導入する際は、自社の営業課題や戦略に合った指標を選定し、継続的に改善サイクルを回すことが大切です。
その際、過剰な機能性やコストに流されることなく、自社の目指す分析にジャストフィットしたツールを厳選して導入するようにしましょう。
正しくツールを選べた暁には、より筋肉質なハイパフォーマー組織を築き上げることが、夢物語ではなくなるはずです。
営業分析ツールに関するよくある質問
Q. CRMとSFAは何が違う?
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報の一元管理や分析を通じて、長期的な関係性の構築や顧客満足度の向上を目的とした仕組みです。
顧客の購買履歴や問い合わせ履歴を分析することで、適切なタイミングでのアプローチやサービス改善に活かす試みです。
一方、SFA(Sales Force Automation)は営業活動そのものを強化するための概念で、案件管理・リード管理・パイプラインの進捗可視化などを重点的に捉えます。
両者の違いを簡潔にまとめると、CRMは「顧客中心」、SFAは「営業活動中心」という焦点の違いでしょう。
実際の営業現場では、CRMで顧客基盤を強化しつつ、SFAで効率的に営業プロセスを回すといった形で、区別して使用されるケースも多く見られます。
Q. 営業ツールの導入にかかるコストはどのくらい?
営業ツールの導入コストは、ツールの種類や機能の充実度、提供形式(クラウド型かオンプレミス型か)によって大きく異なります。
小規模企業向けのシンプルなツールであれば、月額数千円程度から導入可能な場合もありますが、大企業向けに高度なカスタマイズや多機能を備えたシステムでは、初期費用や月額費用が高額になる傾向があります。
また、利用人数が増えるごとに料金が加算される「ユーザー課金型」や、オプション機能追加によってコストが膨らむケースもあるため注意が必要です。
導入前には、単なる料金比較ではなく、自社の営業規模や業務フローに適したプランを選び、長期的な投資対効果(ROI)を見極めることが重要となります。
貴社に最適な
ソリューションをご紹介
-
ワンクリックで
クラウドソーシング可能 -
様々な角度から
瞬時にデータ分析 -
フォローのタイミングを
逃さず管理



