取材代行会社おすすめ10選|料金や選び方を解説

取材のアポ取りやインタビュー、原稿作成など、コンテンツ制作の負担が増す中で、こうした工程をまとめて任せられる「取材代行サービス」に注目が集まっています。
本記事では、取材代行サービスの選び方や依頼時の注意点、信頼できる代行会社10選を厳選してご紹介します。
業界理解があるプロに任せ、質の高い記事を安定的に生み出したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
おすすめの取材代行会社10選

コンテンツマーケティングが重要視される現代において、読者の心を掴む質の高い記事制作は企業の大きな課題です。
まずは、「質の高い取材記事を効率よく外注したい」「自社業界に精通したライターに任せたい」とお考えの企業担当者に向けて、実績と専門性を兼ね備えた取材代行会社を厳選して10社ご紹介します。
各社の強みやサービス内容をわかりやすく解説するので、自社に合ったパートナー選びの参考にしてみてください。
株式会社アナザーパス
株式会社アナザーパスが提供する「TEXPERT(テキスパート)」は、WEB制作業界でも珍しい、取材記事に特化した専門サービスです。
テキスパートの最大の強みは、インタビュー力と文章力を兼ね備えたライターと専属ディレクターが2名体制で一貫して取材記事制作にあたること。
取材対象者の深い想いや考えを自然に引き出し、専門的な内容であっても読み手の心に響く「読みやすさ」と「面白さ」を両立させた記事を生み出します。
求人・広報・ブランディング・タイアップ取材記事など、多岐にわたる記事制作に対応可能です。
さらに、企画考案や写真撮影といったオプションも充実しており、4記事以上の発注で初期費用が無料になるため、継続的なコンテンツ制作を検討している企業にもおすすめの取材代行サービスです。
株式会社声音
読む人の「脳裏に音が浮かぶ」文章で、取材対象者の声と思いを形にするのが株式会社声音(こわね)の取材代行サービスです。
企業が伝えたいメッセージをインタビュー経験豊富なライターが丁寧にヒアリングし、第三者ならではの客観的な視点から『読者の心に響くストーリー』として言語化してくれます。
大手企業や著名人の取材実績も豊富で、メディア運営や企画立案まで一貫して依頼できる点も大きな魅力のひとつです。
企業の広報・PRはもちろん、自分史制作や社内報にも活用されています。
合同会社ONE LIGHT
ONE LIGHTは、メディアのインタビュー取材から社内報・採用サイトの社員インタビュー・イベント取材・サービスの導入事例まで、幅広いニーズに対応可能な取材代行会社です。
取材から制作まで一貫して対応できる体制に加え、演劇やミュージカル業界に特化したメディア「Audience」を運営するなど、十分な実績も兼ね備えています。
また、プロのカメラマン手配や撮影ディレクションも可能で、オンライン取材と対面取材の両方に対応しているため、フレキシブルな対応が期待できます。
インタビュー記事の執筆はもちろんのこと、「取材写真にもこだわりたい」「コンテンツの魅力を最大限に引き出したい」と考えている企業にとって、長く付き合えるパートナーとなるでしょう。
株式会社メディアリーチ
豊富な実績と高い専門性を誇るメディアリーチは、全国対応の取材代行サービスを提供しています。
新聞社や出版社出身の経験豊富な取材スタッフが多数在籍し、医療・金融・不動産・医療・美容・人材・法律等のYMYL(Your Money Your Life)領域を含む幅広い業界の取材に対応。
オンライン・現地取材の両方に対応し、依頼者の意図や目的を深く理解した上で、的確な質問力で深い洞察や魅力的なエピソードを引き出します。
10年にわたる自社メディアの運営実績と、1000名超のライターネットワークを活かし、目的に応じた高品質な取材コンテンツを提供しています。
そのため、自社のブランディングやリード獲得に繋がる「プロフェッショナルな取材代行」を求めている企業には特におすすめです。
株式会社センターグローブ
株式会社センターグローブが提供する取材記事代行サービス「ミキタス」は、SEOメディア運営の実績を活かした、取材力とコストパフォーマンスに定評のある取材代行サービスです。
「見る・聞く・足す」をコンセプトに、高品質でありながら業界最安値クラスの価格を実現しています。
また、厳しい基準をクリアしたインタビュアーとカメラマンが全国各地にスタンバイしており、スピーディーな取材対応が可能な点も大きな特徴のひとつ。
「撮影のみ」や「インタビューのみ」といった部分的な依頼にも対応し、ヒアリングシート作成からサイト反映まで一貫してサポートしてくれます。
1件25,000円からという手頃な価格設定に加え、回数券の購入でさらにお得になるプランもあるため、品質と対応力を両立した「高コスパ」なサービスを探している企業はもちろん、個人の方にもおすすめの取材代行サービスです。
スタジオ・ウーフー
スタジオ・ウーフーは、10万件以上の実績を持つ編集プロダクション。
全国47都道府県にクリエイターが在籍しており、迅速な現地取材で臨場感あふれる記事制作が可能です。
特に注目すべきは、FP1・2級、税理士、医師など多様なジャンルの有資格者が多数在籍している点。
これにより、専門的な内容はもちろん、他社では対応が難しい領域の取材にも柔軟に対応できます。
また、専任ディレクターが、スケジュール管理や質問シート作成などの細かな業務をサポートし、スムーズな取材代行を実現します。
大手企業との取引実績も多数あり、最低1記事から依頼できるため、まずはテストライティングで品質を確認したい企業にもおすすめです。
Hub Works
Hub Worksは、「インタビュー×SEO」の両軸から成果につながる取材記事を提供する取材代行会社で、「AIでは生み出せない一次情報に基づいたオリジナルコンテンツ制作」を強みにしています。
SEOノウハウを持つ専門チームが、キャスティングからインタビュー・記事化までを一貫して対応。
さらに、医療業界やDX・IoT・AIなどのIT業界に強みを持ち、提携する500名以上の専門家や監修者の中から、最適な取材対象者をアサイン可能です。
ウェビナーやインタビュー動画からの記事制作も可能で、多様なコンテンツ展開を視野に入れている企業にとって効率的な取材代行が期待できます。
料金プランは「単発」「月3本」「月10本」の3種類を用意しており、10本プランの場合は1本あたりの割引にも対応。また、執筆数はプラン以外でも柔軟な対応が可能です。
ネイビープロジェクト
「わかりやすいをきわめる」をコンセプトに掲げるネイビープロジェクトは、論理的かつ伝わりやすい文章表現に定評のある取材代行会社です。
編集者・ライター歴10年以上のベテランが構成から執筆まで対応し、構成案や質問票の修正にも柔軟に対応。撮影オプションもあり、全国取材にも対応しています。
さらに、初稿納品後の手厚い品質サポートも大きな魅力のひとつです。
原稿は3回まで修正可能で、納品後も丁寧なフォローが受けられるため、初めての企業でも安心して依頼できます。
ネイビープロジェクトは、「重要な記事」や「失敗が許されない取材」など、ここぞという時にプロの力を借りたい案件時に頼りになる取材代行会社です。
Craudia
Craudia(クラウディア)は、取材・撮影・執筆をワンストップで依頼できる柔軟性の高い取材代行サービスです。
自社メディア運営で培ったノウハウをもとに、100名以上のライターが取材から執筆までを担当。地方取材や専門分野のインタビューにも対応しており、撮影やデータからの記事化も可能です。
1記事からの依頼はもちろん、月10本以上の大量発注にも柔軟に対応し、「基本プラン」「原稿だけプラン」「撮影だけプラン」など、ニーズに合わせた最適なプランを提案してくれます。
スピーディーかつ柔軟な取材代行を求める企業はもちろんのこと、初めて取材代行を依頼する企業にもおすすめです。
未知株式会社
出版社出身のインタビュアーとWebマーケティングのプロがタッグを組む未知株式会社は、成果につながる戦略的な取材記事を得意とする取材代行会社です。
累計1万本超の制作実績があり、100以上の業界で培った質問力と編集力を活かして、読者の心に届く記事を制作します。
未知株式会社の最大の強みは、採用率8%の厳選されたライター陣と、厳しい品質基準を持つ編集チームが、貴社専属で徹底的にサポートしてくれる点です。
満足度96%を誇る専属ディレクターが企画設計から取材、記事納品まで伴走してくれるため、BtoB領域でも安心して任せられます。
取材代行サービスを選定する際の4つのポイント

ここからは、取材代行サービス選定時に確認しておきたい重要なポイントを4つご紹介します。
取材代行サービスを活用することで、質の高いコンテンツを効率よく発信できます。
しかし、依頼先選びを誤ると期待通りの成果に繋がらないばかりか、工数やコストが無駄になってしまう可能性も考えられます。
自社の目的に合ったパートナーを見極めるためにも、これからご紹介する4つのポイントをぜひ参考にしてみてください。
得意なジャンルや業界が自社と合っているか
取材代行を依頼する際は、対象サービスが自社業界に精通しているかどうかをしっかり確認しましょう。
特に、ITや医療、金融といった専門性の高い分野では、「その業界での取材経験が豊富であるか」「専門知識を持ったライターやディレクターが在籍しているか」といった点を重点的に確認する必要があります。
知識不足のライターが担当した場合、取材相手の話を正確に理解し、読者に伝えることが難しくなってしまうからです。
専門用語の誤用や内容のズレを防ぎ、読者にとって本当に価値のある、信頼性の高いコンテンツを提供するためには、各取材代行会社の公式サイトで公開されている過去の取材実績やポートフォリオをチェックし、求めている記事のテイストや品質と一致するかを見極めましょう。
対応範囲はニーズを満たしているか
取材代行サービスの対応範囲は会社ごとに異なります。
記事執筆だけでなく、企画構成・アポ調整・取材・写真撮影・文字起こし・校正など、取材・制作プロセスを一括で依頼できるかどうかを確認しておくと、後の業務負担を大きく減らせます。
また、記事の構成や企画段階から相談に乗ってくれる柔軟な対応力があるかどうかも重要なチェックポイントです。
戦略的なコンテンツづくりを目指すなら、構成や企画などの初期段階から伴走してくれるパートナーを選びましょう。
事前相談などがある場合は、どこまで任せられるかを明確にしておくと安心です。
ライターやディレクターの質は高いか
記事の完成度は、担当するライターやディレクターのスキルに大きく依存します。
特に取材代行では、質問力・傾聴力・構成力といった文章力以外のスキルも多く求められます。
質の高いライターは、取材相手から本音を引き出す優れた「コミュニケーション能力」と、得られた情報を整理し、読者にとって分かりやすく魅力的に伝える「構成力」を兼ね備えています。
ライターが「聞く力」に長けていないと、相手の本音や魅力を引き出せません。
また、初回打ち合わせでのやり取りや提案の質も重要な判断材料です。
構成案が的確か、納品物が論理的で読みやすいか、過去実績のレベル感などを総合的に判断し、信頼できるライターやディレクターが担当してくれる取材代行会社を選びましょう。
料金体系と納期は明確か
取材代行サービスの料金体系は業者によってさまざまです。
「文字単価」なのか「記事単価」なのか、また取材費や交通費、写真撮影費用などが含まれているのかを詳細に確認する必要があります。
オプション費用が発生する場合も、その内容と金額を事前に把握しておきましょう。
また、初稿の納期や、修正対応の回数・範囲についても、契約前にしっかりとすり合わせることが大切です。
納期が不明確だと、全体スケジュールに支障が出てしまう可能性がありますが、これらの条件が明確であれば、安心してプロジェクトを進めることができ、予算オーバーや納期遅延のリスクを回避できます。
金銭トラブルを避けるためにも、見積書や納期スケジュールの提示を事前に依頼した上で、信頼できる取材代行会社を選びましょう。
取材代行を利用するデメリット2選
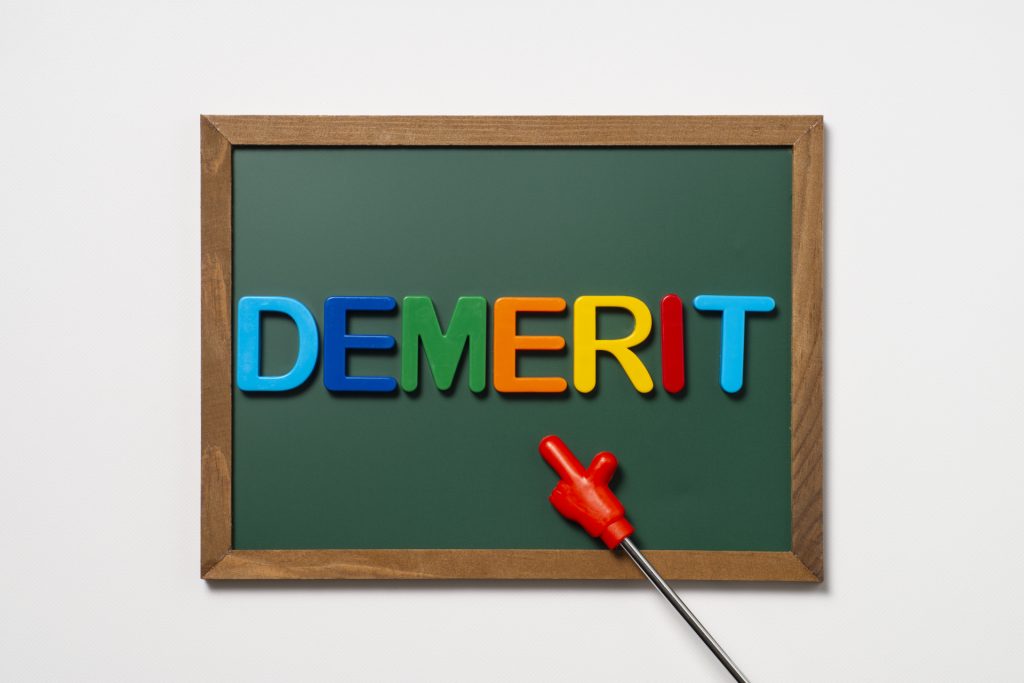
取材代行サービスにはさまざまなメリットがある反面、注意すべきデメリットも存在します。
外部に業務を委託する以上、コストや情報共有に関する課題は避けて通れません。
ここでは、取材代行サービスの利用を検討する際に押さえておきたい2つのリスクとその対策方法をご紹介します。
メリットだけでなくデメリットも把握した上で、自社に合った取材代行サービスを選びましょう。
依頼費用とコミュニケーションコストがかかる
取材代行サービスを外部に委託する以上、当然ながら費用が発生します。
特に、高品質な取材記事や専門性の高い分野のコンテンツを求める場合、その依頼費用は決して安価ではありません。
カメラマンによる写真撮影や動画制作まで依頼するとなると、追加料金が必要になるケースがほとんどです。
また、費用面だけでなく、コミュニケーションコストも考慮しなければなりません。
自社の事業内容や取材の目的、伝えたいメッセージのニュアンスなどを取材代行会社に正確に伝えるためには、事前の打ち合わせや資料準備に一定の時間と労力を割く必要があります。
こうしたコミュニケーションコストを軽減するには、実績が豊富で企画・進行管理に慣れた取材代行会社を選ぶのが効果的です。
自社の意図を的確に汲み取り、スムーズに形にしてくれるパートナーであれば、負担を抑えながらも高品質なコンテンツが制作できるでしょう。
情報のニュアンスが正確に伝わらないリスクがある
取材代行を利用する際に懸念されるのが、「情報の細かなニュアンスや温度感が正確に伝わらない」といったリスクです。
外部のライターが取材を行う場合、たとえ入念なヒアリングを行ったとしても、社内の人間しか知り得ない組織文化やプロジェクトの背景、あるいは取材対象者の微細な感情の動きまでを完全に汲み取るのが難しい場合があります。
これにより、完成した記事が意図したものとわずかに異なる印象を与える可能性も否定できません。
このような情報のズレを防ぐには、事前に伝えるべき要点を整理し、必要であれば取材に同席するのが効果的です。
さらに、初稿の段階でしっかりとファクトチェックを行うことで、より正確で魅力的な記事へと仕上げることが可能になります。
取材代行を利用するメリット3選
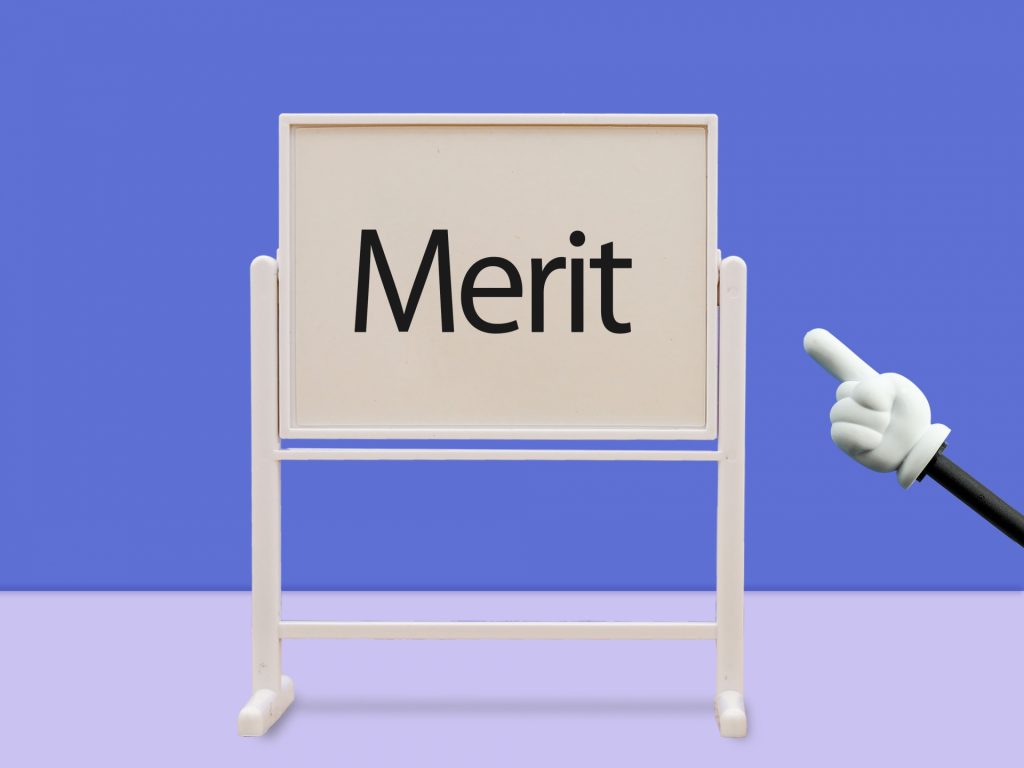
取材記事代行サービスの導入は企業の信頼性やブランド価値を高める上で非常に有効な手段です。
ここでは、取材代行サービスを導入することで得られるメリットを3つの視点からまとめました。
取材代行サービスの導入を検討している方は、比較・選定をする際の参考にお役立てください。
プロ品質の記事で、コンテンツの価値が向上する
取材代行サービスを利用する最大のメリットは、プロのライターやディレクターによって作成してもらえるという点です。
構成段階から編集のプロが関わることで、読者にとってわかりやすく、自社で制作するよりもはるかに質の高い記事が完成します。
特に、自社では見落としがちな強みや魅力を第三者の視点で客観的に引き出してくれる点は、取材代行サービスを利用する大きなメリットと言えるでしょう。
読者にとっても、客観的な視点で語られる情報は信頼性が高く、より深く共感を得やすくなります。
結果として、ブランドイメージの向上やコンテンツ全体の価値を高めることにも繋がるでしょう。
取材や記事作成にかかるリソースを削減できる
コンテンツ制作、特に取材を伴う記事の作成は、アポイント調整から実際の取材・文字起こし・執筆・校正に至るまで、多岐にわたる煩雑な業務を伴います。
これらの工程すべてを自社で担う場合、担当者に大きな負担がかかるケースも少なくありません。
取材代行を活用すれば、記事制作にかかる煩雑な業務を全て外注することができます。
取材対象とのアポイント調整・構成案の作成・インタビュー・原稿の執筆や修正対応まで、すべてをワンストップで任せられるのが大きな魅力です。
その結果、担当者は本来のコア業務に専念でき、生産性の向上にも繋がります。
また、制作フローが整っている取材代行会社であれば、短期間での納品も可能で、タイムリーな情報発信が実現できます。
コンテンツ制作におけるリソースの最適化を図りたい企業にとって大きなメリットとなるでしょう。
高品質な一次情報を獲得できる
取材代行を利用するもうひとつの大きなメリットは、信頼性の高い一次情報を得られるという点です。
専門家や顧客などへの直接取材により、検索では得られない生の声や実体験を文章化できるため、オリジナリティあふれるコンテンツを制作できます。
さらに、こうした一次情報は、Web記事だけでなく、営業資料・ホワイトペーパー・パンフレットなど、他の媒体にも活用可能です。
取材代行を導入することで、企業独自の強みを多角的に発信できるようになり、情報発信の質・量ともに大きく向上させることができます。
まとめ|取材代行は、コンテンツの質と量を両立する有効な一手
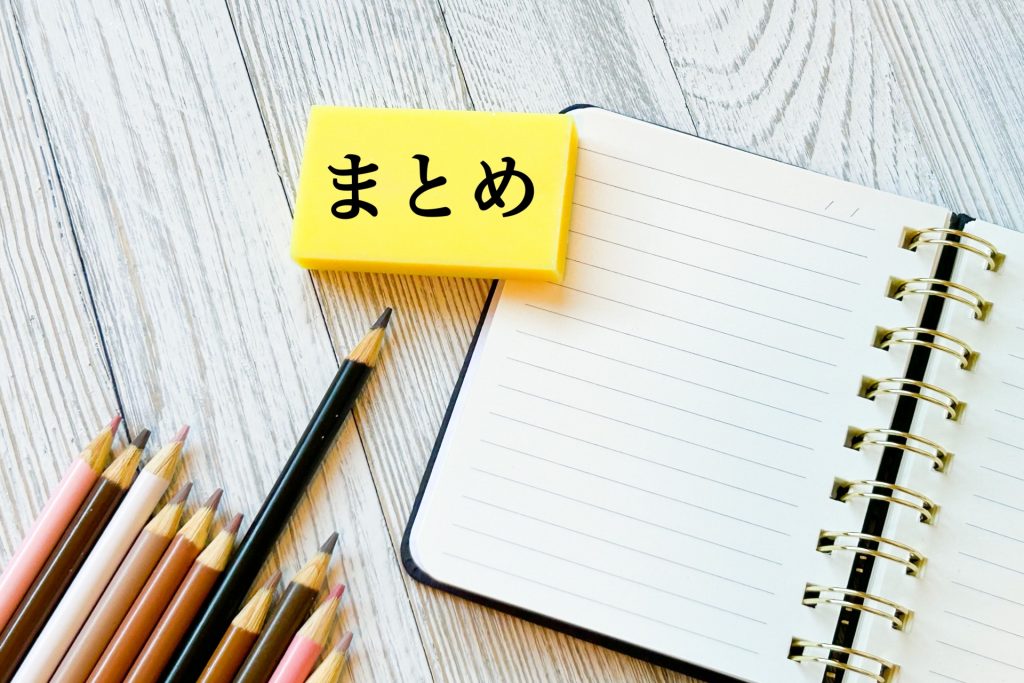
取材代行は、アポイント調整から取材、執筆、撮影までを専門のプロに一括で委託できるサービスです。
取材に関わる業務を社内で抱え込まずに済むため、リソースの最適化とコンテンツ品質の両立が実現できます。
特に、業界知識が求められる分野では、経験豊富なライターやディレクターが取材を代行することで、自社の魅力を正確かつ客観的に伝えられる記事が完成します。
結果として、リード獲得やブランド強化にも貢献する高品質な一次情報を安定的に発信できるようになります。
ただし、取材代行を導入する際は、サービスの対応範囲や得意分野、品質管理体制、料金体系などを事前に確認し、自社の目的と合致しているかを見極めることが重要です。
自社に合った取材代行をうまく活用すれば、コンテンツの質と量の両立が可能になり、リード獲得やブランディングの強化にも大きく貢献するでしょう。
取材代行に関するよくある質問
Q. オンラインでの取材も可能か?
ほとんどの取材代行サービスが、オンライン取材に対応しています。
ZoomやGoogle Meetといったオンライン会議ツールを活用することで、全国どこにいる相手ともスムーズにインタビューを実施することができます。
オンライン取材の最大のメリットは、移動時間や交通費といったコストを削減できる点です。
これにより、予算を抑えながらも、全国各地の専門家や企業の担当者など、幅広い取材対象者にアプローチできるようになります。
また、スケジュール調整の柔軟性も高まるため、多忙な取材対象者でも取材に応じやすくなるでしょう。
ただし、オンライン取材では、対面取材に比べて細かなニュアンスや表情が伝わりにくい場合もあるため、事前に取材代行会社とコミュニケーション方法について確認しておくことをおすすめします。
Q. 修正は何回までできるか?
取材代行サービスでは、修正対応の回数を「2回まで」「初稿納品から7日以内」など、あらかじめ明確に定めている場合が多いです。
通常の表現修正や軽微な変更には無償対応してくれる一方で、構成そのものの大幅な変更や、追加の取材が必要になるような修正は別料金となるケースも少なくありません。
そのため、契約を締結する前に、修正の回数や範囲について必ず確認し、合意しておくことが重要です。
期待通りの記事を制作するためには、事前の打ち合わせで取材の目的や記事の方向性を明確に伝え、初稿の段階で認識のズレがないよう、密にコミュニケーションを取ることが何よりも大切になります。
貴社に最適な
ソリューションをご紹介
-
ワンクリックで
クラウドソーシング可能 -
様々な角度から
瞬時にデータ分析 -
フォローのタイミングを
逃さず管理



