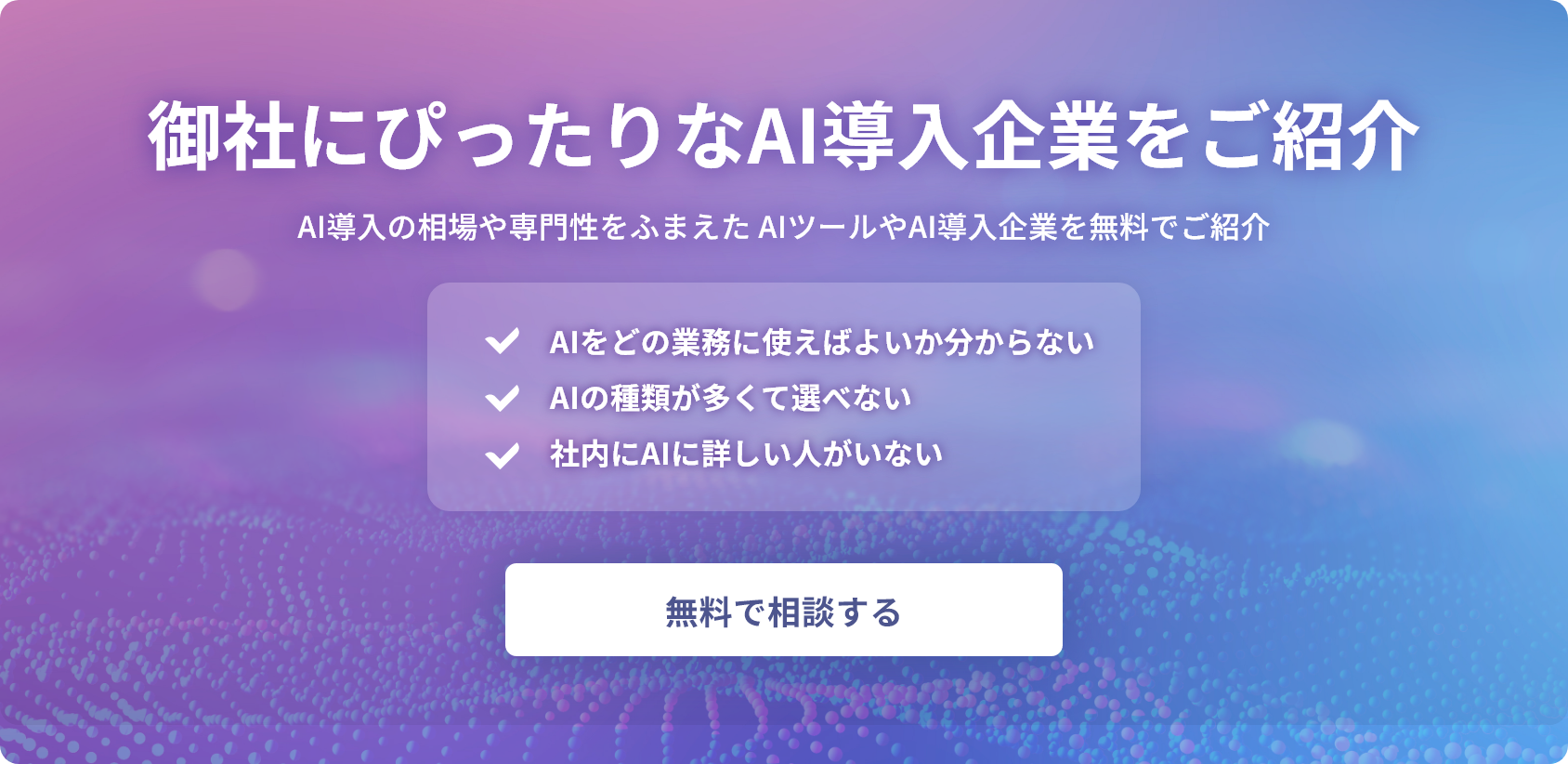生成AIは「知っている」段階から「業務に組み込む」段階へと進み、導入の巧拙が成果を左右するフェーズに入りました。
一方で、要件定義やガバナンス整備、社内教育まで含めると自社だけでの推進は難易度が高くなります。
そこで本記事では、実装と運用まで伴走する生成AI導入支援のおすすめ企業を厳選し、比較の視点も整理しました。
まずは小さく試して大きく伸ばすための“迷わない選び方”を押さえ、最短距離で成果へつなげましょう。
各社で生成AIツールの導入が著しく進んでいますが、自社の課題に即したツールはどのような機能を搭載しているのでしょうか。
「どのサービスを選べばいいかわからない」という方は、AI活用研究所に相談するのもおすすめですので、興味のある方はぜひお問い合わせください。
>>AIをもっと活用しやすく!今すぐAI活用研究所へお問い合わせください。

生成AI導入支援サービスおすすめ10社
NTTデータ GenAIソリューション

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | 企業契約:月額+個別見積(要問い合わせ) |
| 支援内容 | 要件定義、RAG実装、API連携、セキュリティ設計、教育・運用 |
| 公式ページ | https://www.nttdata.com/jp/ja/services/generative-ai/ |
大規模導入のプロジェクト管理とセキュリティ要件への適合力に強みがあります。
RAGや業務自動化のテンプレートが揃っており、既存システムとの連携設計までワンストップで伴走します。
公共や金融で培ったガバナンスの知見をテンプレ化し、監査ログや閉域構成にも対応可能です。
PoCから本番運用、内製化の支援まで段階的なロードマップを提示してくれます。
全社展開を見据えた運用設計と教育プログラムで、定着までの時間を短縮できます。
| 口コミ |
|---|
| 「AI Agentによるクリエイティブ業務支援ソリューションの開発により、非専門人材でも店舗POP等を短時間かつ低コストで作成できるようになった。」|AWS Japan |
| 「生成AIを活用したSmartAgentにより、業務プロセス全体でAI活用を進め、複雑タスクの自動化と生産性向上を実現している。」|NTTデータ |
NEC Generative AI Consulting

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | コンサル契約:個別見積(要問い合わせ) |
| 支援内容 | PoC、評価設計、RAG / 要約、権限・監査、教育・保守 |
| 公式ページ | https://jpn.nec.com/LLM/index.html |
日本語最適化モデルや評価基盤と合わせ、企業内の品質管理プロセスづくりを得意とします。
導入後の精度劣化を防ぐための評価指標や運用ルールを、現場で回る形に落とし込みます。
業界規制に応じたデータ取り扱いと権限設計を明確化し、監査対応の手戻りを抑えます。
短期PoCで効果検証→段階展開のプランを提示し、投資判断を支援します。
国内サポートとSIネットワークが厚く、長期運用でも安心感があります。
| 口コミ |
|---|
| 「多くの社員が日常的に活用して業務効率の向上を実感している。」|クラウドWatch |
| 「LLM『cotomi』を基盤に、セキュアかつ迅速な運用環境とポリシー体系を整備し、業務定着を図っている。」|ニューラルオプト |
富士通 AIトランスフォーメーション支援
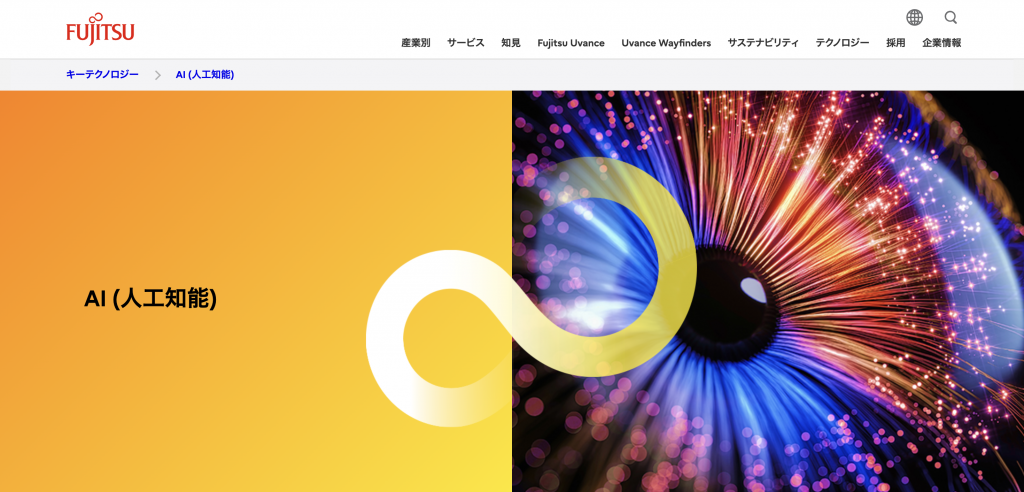
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | PoC / 本番プラン:要問い合わせ |
| 支援内容 | BPR設計、RAG/自動化、匿名化・監査、運用改善 |
| 公式ページ | https://global.fujitsu/ja-jp/technology/key-technologies/ai |
業務BPRとあわせて生成AIを組み込むアプローチで、部門横断の効果創出を狙えます。
既存IT資産を活かすハイブリッド構成に対応し、リスクとスピードのバランスをとります。
データ匿名化やモニタリングなどのガバナンス面もテンプレ化され、立ち上げが速いです。
導入後は継続改善サイクルを伴走し、精度とコストの最適化を図ります。
グローバル対応も可能で、海外拠点を含む展開も見据えられます。
| 口コミ |
|---|
| 「生成AIの社内利用が1年半で10倍に増加し、現在では毎日3万人以上がAIを業務に活用している。」|note |
| 「生成AIを活用した設計支援により、プログラム仕様書などの設計情報において約40%の品質改善が確認された。」|Fujitsu公式 |
ABEJA Generative AI Suite導入支援
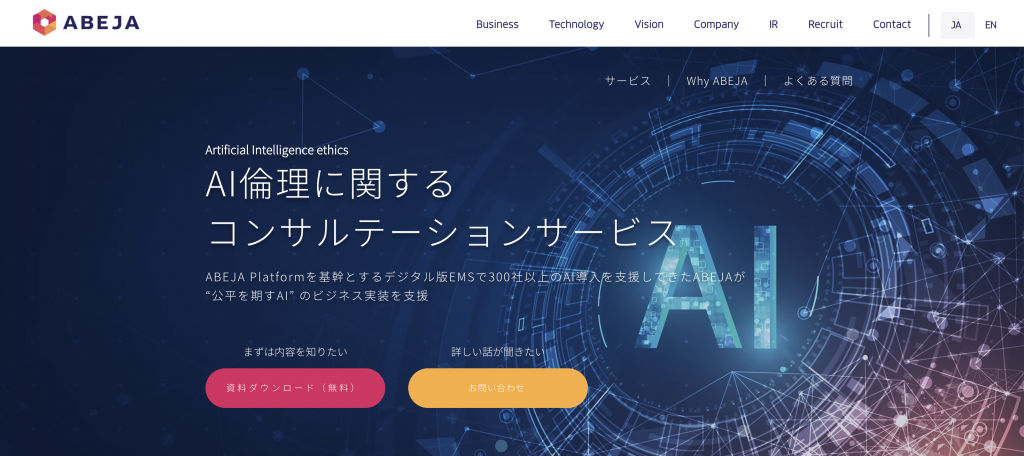
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | 月額+従量(要問い合わせ) |
| 支援内容 | RAG、商品説明 / FAQ生成、連携・ダッシュボード、伴走 |
| 公式ページ | https://www.abejainc.com/ai-ethics |
小売・ECのデータ活用に強く、商品説明生成やFAQ自動化など売上直結のユースケースが得意です。
在庫・顧客・FAQのデータ連携を前提に、RAGと運用ダッシュボードを短期間で構築します。
PoCでKPIを可視化し、改善の仮説検証を高速に回せる体制を整えます。
既存MA / CRMとの接続が柔軟で、置き換え不要の拡張が可能です。
伴走型支援で現場定着までフォローし、内製化にも対応します。
| 口コミ |
|---|
| 「ミッションクリティカル業務に適した堅牢で安定したAI基盤を提供し、多くの企業から信頼を得ている。」|PR TIMES |
| 「『攻めのガバナンス』を実現し、新規ビジネス創出や業務効率化に貢献する生成AI導入支援が高く評価されている。」|PwC Japan |
PwC Japan GenAI Lab

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | コンサル契約:要問い合わせ |
| 支援内容 | 戦略策定、モデル / データ統制、業務設計、リスク / 法令対応 |
| 公式ページ | https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/analytics/generative-ai.html |
経営アジェンダに紐づく戦略策定から、リスク・法務・税務まで含めた全方位の助言が可能です。
モデル選定やデータガバナンスに加え、業務プロセスの再設計まで一体で支援します。
内部統制や監査要件に沿った運用設計を行い、全社展開の障壁を下げます。
グローバルの知見を国内要件に合わせてローカライズできる点も強みです。
投資対効果のストーリーを明確化し、意思決定を後押しします。
| 口コミ |
|---|
| 「PwCの AI Lab は監査・税務・コンサル部門の専門家が集結し、世界各拠点とAI知見を共有することで日本企業への高度なAI実装支援に活かしている。」|SalesZine |
| 「先端技術を活用した事業構想や支援経験が豊富である。」|PwC公式 |
アクセンチュア GenAI Center of Excellence

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | 企業契約:要問い合わせ |
| 支援内容 | ユースケース実装、連携・監視、コスト最適化、教育 |
| 公式ページ | https://www.accenture.com/jp-ja/services/applied-intelligence/generative-ai |
大規模案件の実装力とスピードが特徴で、マルチクラウド・マルチLLMの最適設計に長けています。
ユースケースカタログを活用し、短期間でPoC→本番を実現します。
運用面では費用最適化とSLA管理を仕組み化し、継続的な改善を標準化します。
チェンジマネジメントとスキルトランスファーも含め、定着まで伴走します。
グローバル事例を横展開できるため、再現性の高い成功パターンを活かせます。
| 口コミ |
|---|
| 「企業の生成AI導入において、実証実験から本番運用へ進展させる支援体制が整っており、顧客案件の45%が本格導入へ進んだ。」|PR TIMES |
| 「ジェネレーティブAIを活用したビジネス変革と競争優位の創出に強みがある。」|アクセンチュア公式 |
Deloitte GenAI Studio
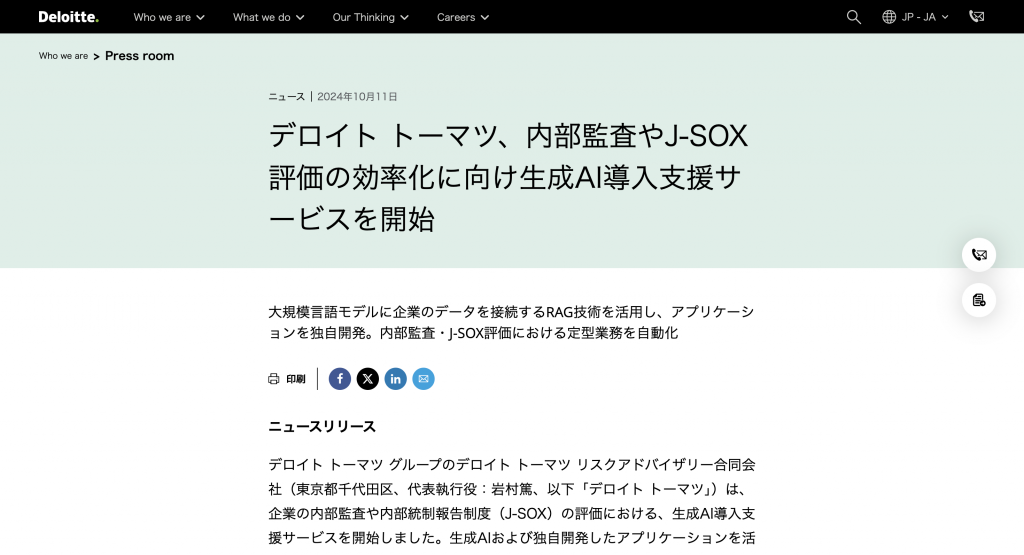
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | コンサル契約:要問い合わせ |
| 支援内容 | プロトタイプ、評価 / リスク、LLMOps、移行・展開 |
| 公式ページ | https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20241011.html |
評価・リスク管理のメソドロジーが充実し、規制産業でも導入しやすい設計を提供します。
プロトタイプ開発と同時に運用要件を固め、移行時の手戻りを減らします。
データ品質管理やドリフト監視など、LLMOpsの仕組み化も支援します。
事業インパクトを定量化し、KPI/OKRでの運用へ落とし込みます。
グローバルナレッジを国内に適合させ、実装速度を高めます。
| 口コミ |
|---|
| 「業界ユースケース集やAIアカデミーを整備してAI人材の育成と利活用を支援している。」|neural opt |
| 「Deloitte では企業が GenAI のパフォーマンスを KPI で評価し、投資効果を可視化するフレームワークを構築している。」|FutureCFO |
BrainPad Generative AI導入コンサル

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | 相談ベース:要問い合わせ |
| 支援内容 | マーケ適用、RAG / 自動化、可視化、研修・内製化 |
| 公式ページ | https://www.brainpad.co.jp/services/professionals/generative_ai_llm_starter.html |
マーケティングデータの分析と生成AIを組み合わせ、広告やCRMの成果改善に直結させます。
コピー生成→テスト→レポートの自動化を構築し、運用の歩留まりを改善します。
社内FAQや提案文のRAG適用など、現場の生産性向上にも実績があります。
経営可視化のダッシュボードで、投資対効果を継続的に検証できます。
研修と内製化の支援により、チームの自走を後押しします。
| 口コミ |
|---|
| 「500件以上の記事を学習したチャットボットをオウンドメディア上に実装し、知識検索や要約を瞬時に実行できるようになった。」|NTTデータ |
| 「Google Cloudと協業したDX立ち上げ支援を通じ、生成AI時代に対応した社会実装の知見を共有している姿勢が評価できる。」|NEC |
AI inside Enterprise AI導入支援

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | 月額+従量(要問い合わせ) |
| 支援内容 | AI-OCR×RAG、権限 / 監査、SaaS / オンプレ、教育 |
| 公式ページ | https://dx-suite.com/lp-001 |
帳票デジタル化や業務自動化の実績を土台に、生成AIの社内展開を加速します。
AI-OCRとRAGを組み合わせ、紙中心の業務からの脱却を短期間で実現します。
権限制御や監査ログなど、運用上のリスク管理が整っています。
SaaSとオンプレ双方に対応し、業務要件に合わせた構成が選べます。
教育コンテンツも用意され、現場の立ち上がりが速いです。
| 口コミ |
|---|
| 「AI inside はDX Suite に RAG を導入し、紙資料を含む業務プロセスの自動化に強みがある。」|neural opt |
| 「OCRエージェントの精度向上支援が可能になった。」|Ledge.ai |
SHO-SAN AI導入コンサルティング

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン / 料金 | MARQ(AI導入支援) 〜5人:50万(税別) 〜10人:75万(税別) 11人〜:98万(税別) |
| 支援内容 | 間取り生成 AI、Web 集客コンサル |
| 公式ページ | https://www.sho‑san.co.jp/ai‑lp/ |
住宅領域を中心に、業務特化ユースケースの設計とPoC実装を得意とします。
小さく試して成果を可視化し、部門横断へ広げる段階導入の設計が明確です。
問い合わせ対応や見積ドラフト生成など、現場の即効性のある領域から着手します。
ノーコード運用やプロンプト研修もセットで、定着率を高めます。
補助金活用の支援もあり、導入ハードルを下げられます。
| 口コミ |
|---|
| 「顧客ヒアリングから最適間取り自動生成までのスピードが格段に早く、営業効率が大きく改善された。」|スタンバイ |
| 「SHO‑SAN のAI × Instagram運用支援で、Instagram投稿の品質が向上し集客が増えた。」|note |
生成AI導入支援を外部活用する5つのメリット
戦略ロードマップ策定で迷走を防止
戦略のロードマップを立てるにあたり、初めて生成AIツールを導入すると具体的な見積もりが甘くロードマップ作成に混乱してしまいます。
しかし、生成AIの導入支援を活用することで、試行錯誤の時間とコストを削減できます。
具体的には、下記のような点を支援会社は提供します。
・ユースケースの優先順位とKPIを明確化
・PoCから本番までのマイルストーンを定義し、意思決定の速度を上げる
・部門ごとの要求を整理し、共通化可能な基盤へ集約
・社内説明を円滑化するための投資対効果のストーリーを設計
社内リソース不足を専門家が補完
社内の限られたリソースの中、プラスアルファで生成AIツールの導入をプロジェクトとして動かすのは非常に困難です。
この時間的・技術的なリソース不足を補ってくれる点も、生成AIの導入支援が得意とする点です。
具体的には、要件定義から実装、運用、教育までの各フェーズに専門家をアサインし、短期間でプロトタイプを仕上げ、社内の温度感を高められます。
また、内製化を見据えたスキルトランスファーも期待でき、属人化を防ぎながら継続運用の基盤を整備することができます。
セキュリティ・ガバナンスをプロの知見で担保
データ取り扱いやアクセス制御、監査対応など、生成AIツールを導入することで綿密に定める必要があります。
生成AIの導入支援を得意とする企業は、この複雑な取り扱いを平準化し、法規制やガイドラインの解釈を運用ルールに落とし込めます。
また、モデル利用に伴うリスク評価と緩和策を体系化するだけでなく、事故発生時のエスカレーションと報告手順も定義します。
これにより、安心して生成AIの全社展開を進める土台が整います。
PoC〜本番展開までのスピードを加速
ユースケースのテンプレと再利用可能なコンポーネントを活用できます。
接続や監視のベストプラクティスを流用し、立ち上げ期間を短縮するだけでなく、検証と改善のサイクルを高速化することで成果創出が前倒しすることができます。
これにより、早期成功事例を社内に共有し、採用の幅を広げることができますので時間価値の最大化につながります。
補助金・法規制対応のワンストップ支援
生成AIの支援会社・ツールは、申請要件に合わせた計画策定と書類作成を支援することも可能です。
この時、国内法や業界ガイドラインに沿った運用で審査の通過率を高めるため、審査通過率の高さが伺えるでしょう。
また、申請・採択後の実績報告や監査対応も並走できる点も特徴です。
費用負担を抑えるだけでなく、導入可否のハードルを下げた結果として、リスクとコストの両面で安心感が増します。
支援会社選定の評価ポイント
業界実績とユースケース事例
まずは、自社と近い規模・業態の事例があるかを確認してください。
特に、成果指標や改善ストーリーが具体的に示されているかが重要で、事例の再現性と横展開の可能性を評価するようにしましょう。
また、担当チームの経歴や体制も見ておきましょう。
具体的には、提案書に記載の体制図を読み込み、過去の導入事例や経験、経歴などを調べると、より安心感を持って選定できるでしょう。
カスタムLLM開発・RAG構築の対応力
データ前処理からベクトルDB、評価指標までを一気通貫で対応できるかを確認します。
この時、ただ一気通貫で対応できるかという網羅性だけを評価するのではなく、品質も含め対応力の高さを評価するようにしましょう。
具体的には、下記のような点を見極めるのが良いでしょう。
・長文や専門語への耐性を高める工夫があるか
・検索品質と生成品質を両立させる設計力
・社内データの安全な取り扱いと権限設計
・運用後の劣化検知
データ保護・コンプライアンス基準
暗号化、鍵管理、アクセス制御、ログ保管期間のポリシーを確認します。
特に、国内データセンターや閉域構成の選択肢があるかを見るのが良いでしょう。
また、第三者監査や脆弱性診断の実績も重要です。
規制業界の導入実績があれば審査が円滑ですので、ポリシー公開と透明性の高さを評価しましょう。
PoC伴走と教育プログラムの充実度
ついで立ち上げ時のハンズオン、利用部門向けの研修、管理者教育の有無を確認します。
そのために、運用ガイドとトラブル対応手順が整備されているかを見ましょう。
ガイドを読み込む際、効果測定とレポートのテンプレの記載があると合意形成が速いです。
また、プロンプトと評価のベストプラクティス共有も重要ですので、定着を左右する“人”の支援が手厚いかを重視しましょう。
費用モデルとROIシミュレーションの透明性
最後は、初期費用・月額・従量・周辺コストの内訳を明示してもらいます。
具体的に評価すべき項目は下記です。
・スケール時の費用カーブとディスカウント条件
・効果の試算モデルが妥当か
・コスト最適化の打ち手提案があるか
上記のような、意思決定に必要な材料を出せる生成AIの導入支援企業は信頼に足り得るでしょう。
生成AI導入支援サービスに関するよくある質問(FAQ)
Q1. PoCは最短どのくらいで実施できる?
要件が明確でテンプレ活用が可能なら、数週間での実施も現実的です。
RAGや要約など定番ユースケースは、再利用可能な部品で短縮できます。
一方でデータ前処理や権限設計が複雑だと期間は延びます。
最初にスコープを絞り、評価指標を明確化することが成功の近道です。
小さく始めて学びを早く得る方が、全体のリードタイムを縮められます。
Q2. 社内データを外部に渡さずに導入可能?
閉域ネットワークやオンプレ構成を選べば、データ持ち出しを最小化できます。
匿名化やマスキングを併用し、個人情報の取り扱いリスクを下げられます。
一部の評価作業のみ、ダミーデータで代替する設計も有効です。
契約で越境移転の禁止やログ保管条件を明確にすると安心です。
要件に応じた技術と運用の組み合わせが鍵になります。
Q3. 中小規模の予算でも相談できる?
PoCスコープを絞り、既存SaaSとノーコードで始めれば負担を抑えられます。
補助金の活用や段階導入で、初期支出を平準化できます。
運用は自走を前提にスキルトランスファーを受けると効果的です。
費用対効果を短期で実証し、段階拡大の根拠を作りましょう。
多くの支援会社が中小向けプランも用意しています。
Q4. 導入後のモデルアップデートは誰が対応する?
支援会社が運用保守に含める場合と、内製チームへ移管する場合の二通りがあります。
更新頻度や評価手順、ロールバックの基準を事前に合意します。
監視とドリフト検知を自動化し、異常時に迅速な対応ができる体制が理想です。
変更履歴と影響範囲を記録し、監査証跡を残します。
内製化を目指すなら、移管計画と教育を早期に始めましょう。
Q5. 失敗しないための社内体制づくりは?
事業責任者のスポンサーシップと、現場横断の推進チームが重要です。
情報システム、法務、セキュリティ、各部門の代表が合意形成に関与します。
KPIと運用ルールを明文化し、定例のレビューで改善します。
成功事例を早期に共有し、巻き込みを強化します。
最小の成功を積み重ね、段階的に全社へ広げましょう。