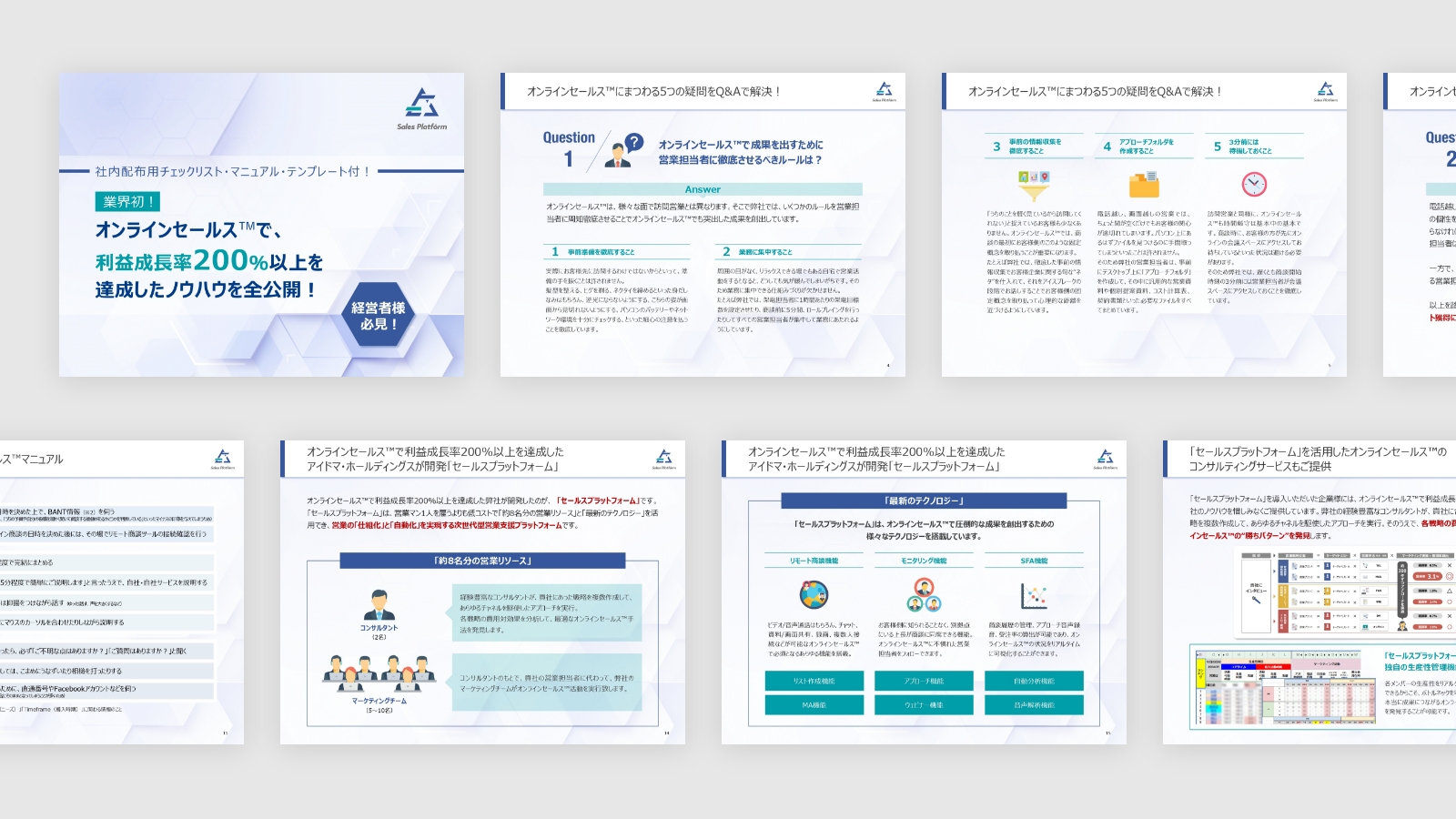人材不足の解消と新規開拓を目指し「Sales Platform」を導入。社内のモチベーションアップ効果も得られた
日本漬物株式会社
代表取締役 後藤 浩孝 様ご利用中のサービス
Sales Platform
- 課題
営業の人材不足を補い、新規取引先を獲得するための方法を模索していた
- 解決策
「Sales Platform」で全国の販売店や旅館などにアプローチ
- 成果
関東の漬物店への納入が決定。契約を延長し、展示会のフォローアップからのビジネスチャンスも狙う
鹿児島湾を望む霧島市福山町。古くから国内屈指の黒酢の名産地として名を馳せるこの地に、創業100年を迎えようとしている老舗の漬物企業・日本漬物株式会社がある。現代表取締役・後藤浩孝氏の祖父にあたる後藤戢(あつむ)氏が1926年に北九州で小さな漬物販売店を創業。やがて福岡県に拠点を移した戢氏は漬物製造を始め、今日まで3代にわたり味と製法を守り続けてきた。
「東京で30年ほど催事や物産イベントなどを担当し、コロナ禍を機に鹿児島に戻りました」と語るのは、2024年に3代目の代表取締役に就任した後藤浩孝氏だ。大学卒業後に民間企業を経て家業に入り、1997年からは同社の販売部門の責任者として東京に赴任。新型コロナウイルスの流行でイベントの中止が相次いだこと、そして高齢となった父親をサポートするために帰郷を決意したという。事業を承継したものの、思うように営業活動ができない日々が続いた。
「私が鹿児島に戻ったとき、社内には営業担当がいませんでした。新規取引先を開拓しようにも、社長業と営業の両立は時間的に不可能だったため、営業支援サービスを探していました」(後藤氏)
後藤氏がアイドマ・ホールディングスと出会った経緯や「Sales Platform」を導入した理由、その後の成果などを詳しく伺った。
ネットで見かけたアイドマ・ホールディングスの広告。テレマーケティングに勝機を感じて導入を決意

「父が鹿児島で製造した『薩摩しぼり』を広く全国にPRするために立ち上げたのが、日本漬物です。デパートでの催事販売をメインに、漬物販売店や旅館などへの卸売りの営業も私が担当していました」と語る後藤氏。高島屋、日本橋三越、伊勢丹といった大手百貨店に顔が広く、催事会場では自ら店頭に立ってきた。
新型コロナウイルスの流行を機に鹿児島に戻り、製造を担ってきた父・正剛氏の企業と事業を統合した。しばらくは営業活動を続けていたが、正剛氏から事業を承継すると日々の営業活動にも支障が出るようになってしまった。
「社長をしながら全国を飛び回るわけにはいきませんし、かといって社内に営業ができる人材もいない状態です。新たに営業担当を雇用するにしても、一人前に育ってくれるまで時間も費用もかかります。良い解決策はないものかと思案していました」(後藤氏)
2024年7月のある日、たまたま見かけたアイドマ・ホールディングスのネット広告。サービス内容に興味を持った後藤氏は、すぐさま問い合わせた。
「私が東京で営業をしていたころは、今よりも個人情報に対する規制が厳しくない時代でしたから、いろいろな名簿を仕入れては営業活動に活用していました。でも今はそのような営業手法を取ることが難しい時代ですから、新規で営業先を見つけるにも苦労します。その点、アイドマさんの持つ膨大なリストを駆使したテレマーケティングは、大きなアドバンテージがあると感じました。
仮に自分たちで電話営業したとしても、断られ続けると途中で心が折れてしまうと思うのですよね。なので、マーケティングのプロにお願いして、営業活動の最初のドアを開けてもらうしかないと思って契約しました」(後藤氏)
「Sales Platform」で社員の意識にも変化が。市場の声をもとにして新商品を開発

契約後は速やかにアプローチ先の選定に取り掛かった。アイドマ・ホールディングスと綿密な打ち合わせを行い、全国の高級旅館や高級和食店、道の駅、漬物店などをリストアップしていった。
「弊社の『薩摩しぼり』を納入していただくのはもちろん、昨今のSNSの影響力もかなり意識しました。例えば、旅館や飲食店などで食事された方々が『薩摩しぼりっておいしいよね』と発信すると、商品の魅力が一気に拡散されます。そうやって商品認知度を上げていくことができれば、今後の営業活動にもプラスになるだろうという目論見もあります」(後藤氏)
かつて担当していた催事販売は、売場で消費者に直接PRすることで商品の認知度を高めてきた。現在はSNSの力にも注目し、さらなる商品認知度アップを狙っている。
アプローチ先の洗い出しと同時に、テレマーケティングに使用するトークスクリプトの準備も進めていった。当初は9月からアプローチを開始する計画だったが、思わぬ事情から1か月半ほどずれ込んでしまう。
「『薩摩しぼり』の原料となる薩摩大根が不作で、数がきちんと確保できるまでお客様へのアプローチの時期を遅らせました。想定外でしたね」(後藤氏)
こうして10月中旬からテレマーケティングを開始すると、次々にサンプル品送付のオーダーが入り、関東地方の複数の漬物店が「薩摩しぼり」の販売に手を上げてくれた。アイドマ・ホールディングスとの月例ミーティングでは、お客様にアプローチした際に寄せられた多くの要望を共有する。そこで、今まで気付かなかった市場のニーズが見えてきた。
「『保存料不使用の薩摩しぼりはありますか?』『内容量の少ないパッケージはつくれますか?』などの声が届いていると聞きました。元々、遠方への発送を想定して保存料を使っていましたし、都市部は鹿児島よりも1世帯の構成人数が少ない傾向にありますからね。テレマーケティングを通じて販売店のリアルな声をちょうだいしました。」(後藤氏)
同社ではさらに、「薩摩しぼり」以外の商品も積極的に開発していく予定であると後藤氏は明かしてくれた。
「鹿児島産のらっきょうを霧島市福山の黒酢で漬け込んだ『黒酢らっきょう』や、べったら漬けも商品化します。営業活動で寄せられた意見をみていると、商品のラインナップを増やしても必ず商機はあると思ったからです。市場のリアルな声や意見は現場にもきちんと共有していて、社員たちは以前よりも新商品開発に俄然乗り気になっています。『Sales Platform』を導入した結果、社内の意識改革も進められた気がしますね」(後藤氏)
「Sales Platform」と展示会の積極活用で、「薩摩しぼり」の味を後世に残していく

「私の祖父が始めたこの企業は、2026年で創業100年を迎えます。私が3代目に就任するにあたり父と話し合うなかで、ひとつだけ決めたことがあります。それは、『薩摩しぼりを100年後も200年後も皆様に親しまれる商品にする』こと。祖父から大切に受け継がれてきた事業を守り続けると同時に、我々が育ててきたこの味を後世に残していく。
そのためには自分たちの資本以上のビジネスをしていく必要があると思い、縁あって知り合った農業法人の傘下に入りました。反対意見もありましたが、これからは一族経営にこだわるのではなく、『薩摩しぼり』の味を守ることにこだわろうと決心しました」(後藤氏)
「Sales Platform」を運用し始めて約半年。商品のバリエーションを増やすとともに、今後は食品関連の展示会への出展も計画するなど、後藤氏は新規取引先の開拓に向けた動きを一気に加速させていくつもりだ。つい先日、「Sales Platform」の契約期間をさらに1年延長した。
「展示会は百貨店や量販店のバイヤーなど、我々のビジネスの発展に欠かせない方々との出会いの場です。名刺交換した方々へのフォローアップなどもアイドマさんにお願いして、今よりもっとビジネスチャンスを拡大させていこうと考えています」(後藤氏)
インタビューの終盤、「Sales Platform」を導入した率直な感想を後藤氏に聞いた。
「スタートの出遅れたことに加え、すぐ年末商戦期が来たので商談が思うように進まない時期もありました。それらを差し引いても、まずまずの成果だったのかなとは思います。ビジネスの場では、最初の交渉から成約まで半年や1年かかるなんてことも少なくありません。
私は以前から“才能にはふた通りある”と思っています。勉強やスポーツで例えるとわかりやすいですが、頭が賢いとか運動神経が良いといった元々の生まれ持ったセンスがひとつ目の才能。もうひとつは、努力し続ける力。結果を出すには後者の方が圧倒的に大事なことですが、継続するというのは非常に難しくて忍耐力も要ります。
これはビジネスでも同じで、今回であればアイドマさんのパフォーマンスを頼りに新たな出会いを得て、さまざまな声に対して柔軟な発想力で応えていく。そしてコツコツと信頼を積み上げていく。結果はおのずとついてくると思っています。弊社だけでは困難なことも、アイドマさんとなら前向きに続けていけると感じています」(後藤氏)
日本漬物株式会社
事業内容
漬物製造、販売