
目次
テンプレートを使って自社の営業リストを作成したい
営業リストにどのような項目を記載するのかを知りたい
営業リストの必要性がわかっていても、どのように準備すればよいのか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
営業リストのテンプレートには、有料と無料で利用できるものがあります。
| 向いている企業 | おすすめの企業 |
|---|---|
| 有料テンプレート | 営業メンバ―がリスト作成に時間をかけることなく営業活動に注力したい企業 |
| 無料テンプレート | 社内でリストのフィードバックを行えたり、リスト作成にリソースを割けられる企業 |
自社の営業目的に合う営業リストを作成できると、活動の情報共有や顧客へのフォローを効果的に実施できるでしょう。
テンプレートを活用したい方に向けて、営業リスト作りに使えるテンプレートの種類と成果を上げやすくなる作り方のコツを紹介します。
なお既存の営業リスト以外に多くの企業リストからターゲットを絞り込みたい場合は、営業自動化サービス「Sales Platform」の活用もおすすめです。
Sales Platformでは、日本全国680万件以上のリストの中から瞬時に潜在的なアプローチ先の企業リストを生成できます。
今なら期間限定で、60,000件以上の企業リストと6,000件の電話営業を無料プレゼント中です。営業の効率化やリソース不足を解消したい方は検討してみましょう。

営業リストを用意する際には、まず「有料=コストをかける」のか「無料=時間をかける」のかを決めます。
それぞれのパターンでのメリット・デメリットを知り、自社製品やサービスにマッチするのはどちらなのかを判断しましょう。
| メリット | デメリット | 特徴 | |
| 有料 | ・営業メンバ―がリスト作成に時間をかけることなく営業活動に集中できる ・サービスの閉鎖・移転など、相手とコンタクトができないといったトラブルが少ない ・リソース不足となる心配がない ・ターゲット層の抽出方法を変えることで、ビジネスの幅を広げることができる | ・コストがかかること ・ターゲット層がズレていたとしても軌道修正にもコストがかかること ・競合他社も同様のリストを使用していた場合、バッティングする恐れがある | ・データ販売会社にターゲット層指定でリストの作成を依頼する ・情報収集ツールを使用し、自分でデータを抽出する ・ビジネス系サイトのテンプレートを使用して自作すればリストは無料になる |
| 無料 | ・製品に詳しいものがターゲットを選定するので、効果の上がりやすいリストとなる ・社内のフィードバックを得やすいので、リスト作業の軌道修正が容易 ・ネット検索しながら、製品のアピール方法などの着想をしやすい ・データ会社との契約金や情報収集ツールの月額使用料などがかからない | ・人材リソースを検索作業に充てなければならない ・人件費がかかる ・想定以上に時間がかかった場合、営業活動のスタートが遅くなる | ・ウェブ上で簡単にアクセスできる ・多様な業界やビジネスに対応する汎用テンプレートが豊富にある ・特定のビジネス要件に合わせてカスタマイズする必要がある |
有料で提供される営業リストには、データ販売会社にターゲット層を伝えてリスト化してもらうケースと、情報収集ツールを利用し自身でデータを抽出するケースがあります。
有料のテンプレートを利用すれば、営業チームがリスト作成に費やす時間を削減して、直接営業活動に専念できるようになります。さらにサービスの閉鎖や移転などの接触不可能なトラブルが少なくなり、リソースの不足に悩まされることもありません。
一方でコストや競合とのバッティングなど、経済的および戦略的なリスクを伴います。
有料テンプレートの利用前には、テンプレートにかかる費用と期待できるビジネスの成果を慎重に分析しましょう。
無料テンプレートは、インターネット上で容易に見つけられ、誰でもアクセスして利用できます。さまざまな業種やビジネスモデルに適応可能なテンプレートが多く、広い範囲のニーズに対応できるのが魅力です。
メリットとして、データ販売会社との契約や情報収集ツールの利用料など、追加の金銭的負担が発生しない点が挙げられます。
ただしリスト作成に要する人的リソースの確保が必要であり、テンプレートの更新やデータの最新性の保持はユーザー自身の責任です。
リスト作りに時間をかけてしまうと、その分実際の営業活動に遅れが出てビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。
「リスト作りにコストをかけられないから無料で」と考える人もいるでしょう。しかし人員や時間の制約が厳しい企業の場合は、無料テンプレートの利用を慎重に検討すべきです。
営業リストにテンプレートを使用する理由は、業務の迅速化と効率向上を図るためです。
テンプレートを活用すれば、営業担当者は書式の作成や必要項目の検討に時間を費やすことなく、直ちにリスト作成に着手できます。営業活動への移行が速やかになり、より多くの潜在顧客に対して効果的なアプローチが可能です。
さらにテンプレートを実際の業務に適用してカスタマイズを行えば、営業チームのニーズに合った使い勝手の良いリストを作り上げられます。
単なる連絡先リストではなく、営業戦略を推進するための強力なツールとして機能させるためにも、テンプレートを活用した営業リストを作成しましょう。

テンプレートを活用して営業リストを自作する場合、「まずは作ってみる・動いてみる」という積極性が大切です。しかし基のテンプレートが期待するものと違っていては、すべての作業が無駄になってしまいます。
営業リスト運用後の使い勝手をイメージして、以下のの3点についてしっかりチェックしてからリスト作成を始めましょう。
営業リストは作成する人物が少人数であったとしても、運用後は営業セクション全体で利用するものです。
ターゲット情報を深く調べて記載するのも大切ですが、活動の際に欲しい情報がどこにあるのか、追記はどこにどのようにしたらよいのかなどが見渡しにくいリストは避けた方がよいでしょう。
リストの操作に別のマニュアルが必要、使用できるのは一部の人のみなどでは、効率的とはいえません。
「誰がみてもすぐわかる」「いつでも引き継げる」を重視して、シンプルで使い勝手が良いものを選びましょう。
営業リストは、営業支援システム(SFA)や顧客管理システム(CRM)などに発展させ、営業セクション全体で活用できます。
営業担当者の行動を管理するためにスケジュールツールと連携させたり、商談予定をカレンダーと連動させたりしましょう。
ほかにもメールの内容を自動でリスト化したり、在庫管理システムと連携させたりと、自社の営業ツールや他部署との連携に役立てやすいかチェックするのがポイントです。
しかし機能が豊富になるほど、操作性が複雑になって入力の手間が増えたり、システムの横断に時間がかかったりして作業効率が下がります。
必要な情報や連携システムとのバランスを検討しながら、リストを作成していきましょう。
作成した営業リストはクラウド上に格納しておけば、複数人で管理しやすいです。
しかしクラウドはインターネット上の仮想空間であるため、悪意を持った第三者の不正アクセスやウイルス攻撃などのリスクがあります。
高度なセキュリティを求める場合には、社内に専用サーバを設置したり、オンプレミス型のサービスを利用したりといった対策が必要です。
近年は強固なセキュリティ対策をとっているクラウドサービスも増えています。保守管理などの手間やコストを考えると、クラウド利用を選択しても問題ないでしょう。
また利用者のITリテラシーを高めておかなければ、不用意な操作による情報流出の危険もあります。
営業リストや顧客情報は企業の「資産」であることを周知し、情報管理についても適宜教育・研修を実施しましょう。
営業リストのテンプレートを作成する際、おすすめのツールは以下の3つです。
| サービス名 | 特徴 | 有料or無料 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| Sales Platform | ・営業支援ツールと営業代行スタッフがセットになったサービス ・リスト作成、アプローチ、マーケティング、分析まで営業活動のすべてを支援 | 有料 | https://sales-platform.jp/ |
| Sansan | ・元名刺管理サービスの強みである企業情報に注力 ・帝国データバンクとの連携で100万件を超える企業データベース ・SalesforceやMarketo等のCRM・SFA・MAツールと連携可能 | 有料 | https://jp.sansan.com/ |
| BIZMAPS | ・登録企業が170万社以上 ・細分化されたソート機能 ・AIによるレコメンド機能 | 有料 (月100件まで無料) | https://biz-maps.com/ |
おすすめのツールを活用して、テンプレート作成作業の効率化を図りましょう。

| 企業名 | 株式会社アイドマ・ホールディングス |
| ツールの概要 | ・リスト作成 ・アプローチ ・分析 ・SFA ・MA ・リモート商談 |
| 料金体系 | 有料(要問合せ) |
| 特徴 | ・営業支援ツールと営業代行スタッフがセットになったサービス ・リスト作成、アプローチ、マーケティング、分析まで営業活動のすべてを支援 |
| 公式サイト | https://sales-platform.jp/ |
「Sales Platform」は、営業支援ツールと営業代行スタッフがセットになったサービスです。
リスト作成だけでなく、顧客へのアプローチや顧客管理など営業に必要な全機能を備えており、営業プロセスを効率化したい企業におすすめです。
営業支援実績は7,850社以上と長年にわたる豊富な経験から得た知識があるので、信頼して業務を委託できるでしょう。
今なら期間限定で、自社にマッチした企業リスト60,000件と営業スタッフによるテレマーケティング6,000件を無料プレゼント中です。
リスク作成を含む営業プロセス全体を効率化したい場合は、導入を検討してみましょう。

| 企業名 | Sansan株式会社 |
| ツールの概要 | 名刺管理クラウドから、下記の機能を備えた営業DXツールに進化 ・企業データベース ・名刺をデータ化 ・メール署名取り込み ・スマートフォーム ・顧客との接触記録 ・オンライン名刺 ・スマート名刺 ・メーカー商談管理 ・リストチェック ・顧客の人事異動情報 ・企業の最新ニュース配信 ・名刺分析メール配信 ・社員間メッセージ機能 NPO法人向けのプランも用意 |
| 料金体系 | 初期費用+運用支援費用+ライセンス費用(月額)+オプション費用(月額)+Sansanスキャナ(月額) ※機能やサービスに応じて変動するため、詳細な金額は要問い合わせ |
| 特徴 | ・元名刺管理サービスの強みである企業情報に注力 ・帝国データバンクとの連携で100万件を超える企業データベース ・SalesforceやMarketo等のCRM・SFA・MAツールと連携可能 |
| 公式サイト | https://jp.sansan.com/ |
「Sansan」は、元の機能である名刺管理機能をさらに強化した営業DXツールです。
100万件以上の企業データを基に、受注の可能性が高い営業リストを作成できます。また名刺を含む顧客との接点情報を用いて、より効果的なアプローチが可能です。
企業情報には、本社だけでなく支店や支社といった国内拠点の情報が含まれているため、特定の地域やエリアにマッチした精度の高いリスト作成が簡単にできます。
名刺をはじめとした顧客との接点情報を一元管理し全社で共有できるので、顧客管理を効率化させたい企業におすすめです。

| 企業名 | 株式会社アイドマ・ホールディングス |
| ツールの概要 | 国内最大級の企業データプラットフォーム |
| 料金体系 | Free:月100件まで無料 個別購入プラン:5,000円〜 定額プラン5000:3か月で月あたり49,900円~ 定額プラン1000:3か月で月あたり9,980円~ |
| 特徴 | 登録企業が170万社以上 細分化されたソート機能 AIによるレコメンド機能 |
| 公式サイト | https://biz-maps.com/ |
「BIZMAPS」は、170万社以上の企業情報を含む広範なデータベースから、わずか30秒で営業リストを生成するツールです。
大量の企業データだけではなく、基本情報に加えて細かく分類されたソート機能を通じて、高精度のターゲティングを可能にします。
また企業リストは定期的に更新されるため、自身で企業情報を更新する必要がありません。
購入意欲の高い顧客への効果的なアプローチが可能であるため、成約率の向上や取引単価の増加を目指す企業におすすめです。

営業リストを作成する際は、基本的に下記の項目を含めるようにしましょう。
また営業活動を円滑に進めるための情報もまとめておくと良いでしょう。
ただし必ず上記の項目すべてを含める必要はありません。
自社の営業活動に必要な情報を含めれば問題ないため、必要な情報をわかりやすくまとめましょう。

営業リストの質は、その後の活動の成果が上がるかどうかに大きく影響します。
「電話帳を写しただけ」「事業所近くの企業をリストアップしただけ」といった目的意識の薄いリストだと、効果が期待できません。
空振り営業が増えると商談化率・成約率が低下し、営業担当者のモチベーションにも関わります。良質な営業リストを作るコツを、以下の3つの視点から解説します。
営業リストの作成を進める前に、自社製品やサービスのターゲットとなる企業や一般消費者像を明確に定義しておきましょう。
BtoB企業であれば以下のような内容を設定しておくと、効果的なアプローチが実施できます。
ペルソナを定義するとリスト化のための取捨選択がスムーズになり、作業効率も上がるでしょう。
また営業セクション全体でペルソナ共有すれば、統一感のある活動が可能です。ただしペルソナの設定をイメージだけで行うと、実際のターゲット像とズレが生じるリスクがあります。
過去の取引相手の情報や担当者の実像などを反映し、実態に即したペルソナを設定するように心がけましょう。またペルソナの設定の具体例は、以下のとおりです。
| 設定する項目 | 内容 | 注意事項 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 業種の選定 | ターゲットとなる企業の業種を明確に選定する | 自社の製品やサービスがどの業種に最も適しているかを考慮する | ①自社はクラウドベースのプロジェクト管理ツールを提供している。 ②プロジェクト管理の業務が多く発生するITコンサルティング企業をターゲットに選定しよう。 ③ITコンサルティング企業はプロジェクト管理のニーズが高いため、製品価値が最も発揮されるだろう。 |
| 従業員規模の設定 | ターゲットとする企業の従業員規模を決定する | 従業員数によって課題やニーズが変わるため、明確な規模設定をする | ①大手企業だと既に自社のツールを導入している可能性が高いため、従業員規模を300人以上の中規模企業に絞り込もう。 ②中規模企業特有のプロジェクト課題に焦点を当て、より適切なアプローチを考えよう。 |
| 課題やニーズの特定 | ターゲットとなる企業が抱えている課題やニーズを洗い出す | 自社の製品やサービスがどのような価値を提供できるかを理解する | ①ITコンサルティング企業が抱える課題として、プロジェクトの進捗管理が複雑であることが挙げられる。 ②ニーズとして、リアルタイムなプロジェクト進捗の可視化や効率的なチーム連携が求められている。 ③自社の製品が解決できる価値をピックアップしよう。 |
| 経営状況の把握 | ターゲット企業の経営状況を分析し、安定した企業や成長企業を選定する | 経営状況は取引の安定性や提携の可能性に影響を与える要素なので、しっかりリサーチする | ①ITコンサルティング企業の中でも、安定している企業や成長が見込まれる企業を重点的に選定しよう。 ②業績が安定している企業はプロジェクト管理ツールへの投資がしやすく、成長中の企業はスケールに合わせた柔軟性が求められるため、両方のケースで製品価値が認められるだろう。 |
| 担当者のペルソナ設定 | ターゲット企業の担当者に焦点を当て、役職や業務上の課題、情報収集手段などを具体的に設定する | ターゲット担当者が製品やサービスを購入する際のプロセスを理解する | ①ITコンサルティング企業のプロジェクトマネージャーを重点的な担当者とし、その中でも特に新規プロジェクトの進行役であるリーダーをペルソナとして設定しよう。 ②このプロジェクトリーダーが製品の導入において中心的な役割を果たす可能性が高いだろう。 |
営業リストは活動の分母となるため、記載数が多いほどその後の販売数・契約数の増加が期待できます。
そのため大量の情報を効率的に集める方法を検討しましょう。住所や業種といった基本情報は、iタウンページやマピオン電話帳などから集めるのがおすすめです。他にも営業先からもらった名刺の情報を参考にする方法などもあります。
注力している分野を知りたいならリクルート情報から、取扱商品を調べるならECサイトからなど、知りたい情報に合わせて利用するサイトを選定しましょう。
企業情報を深く知るには、それぞれの公式サイトを検索するのも有効ですが「営業リスト作り」のフェーズで企業研究をしていては、時間と手間がかかりすぎてしまう恐れもあります。
一度インターネットから離れ、紙媒体の会社四季報や業界誌など、情報を見渡せるツールを利用するのもおすすめです。
営業リストの情報は「集めて終わり」ではなく、生きた情報として手を入れ続けるのが望ましいです。
社名変更や担当者の異動に対応できていないリストでは、訪問先に失礼にあたり、ファーストコンタクトの印象が悪くなってしまいます。
営業活動で得た最新情報を適時フィードバックするのはもちろん、リスト運用後も定期的にチェックする体制づくりが大切です。
また決算月にはいち早く経営状況を整理して記載し、伸びている分野や課題のある分野を発見できれば、効果的な営業活動につながるでしょう。

自社の営業リストを作成したい場合、有料または無料のテンプレートの活用がおすすめです。
仕事のリソースを優先して営業リストを作成したい場合は、有料のテンプレートを利用しましょう。
特に大量のデータが必要な場合には、作業時間から人件費を考慮して、より成果が上がるリストを用意できる方法を選ぶと効果的です。
無料で営業リストのテンプレートを提供しているサイトは多数ありますが、マクロウイルスなどのリスクがあるため、信頼できるサイトの利用をおすすめします。
さまざまなテンプレートが配布されているので、営業リストのテンプレートを選ぶ際のポイント3選を参考に、複数のツールを比較して導入しましょう。
また既存の企業以外の営業リストを確保したい場合は、Sales Platformの活用が便利です。60,000件の企業リストから、自社に合うアプローチ先の企業を抽出できます。
詳細は無料の資料請求から確認が可能です。
A.営業メンバ―がリスト作成に時間をかけずに活動に注力したいのであれば、有料がおすすめです。
しかしただお金をかければ良いというわけではありません。リサーチのもとターゲティングをしっかり行う必要があります。
A.実際のビジネス環境や営業活動の性質によって異なりますが、少なくとも月に一度はリストを確認し、必要に応じて情報を更新しましょう。
リストの更新はただ単に情報を最新のものにするだけでなく、営業チームが顧客に対してより効果的にアプローチできるようにするための重要なプロセスです。
営業リストは生きたドキュメントであり、顧客情報や市場環境の変化に応じて定期的な更新が求められます。
A.はい。エクセルでも作成可能です。
しかしエクセルなどオフィス系のテンプレートには、マクロウイルスと呼ばれるマルウエアが仕込まれているケースがあります。
ダウンロードする際には、信頼できるサイトを利用するなど注意が必要です。
またエクセルには共同編集機能がなく「〇〇さんのPCに最新版が入っている」「担当者ごとにリストを分割したけれど、統合しようとしたら書式が崩れていた」など、営業セクション全体に使うには不向きな点も考慮しておきましょう。
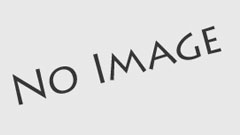 営業DX2024年07月02日営業ツールのおすすめ5選!プロが教える5つの成功事例と4つの選ぶコツ
営業DX2024年07月02日営業ツールのおすすめ5選!プロが教える5つの成功事例と4つの選ぶコツ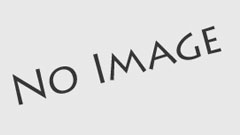 営業DX2024年07月02日テレアポ代行とは?プロが失敗しない選び方とおすすめサービス5選を紹介
営業DX2024年07月02日テレアポ代行とは?プロが失敗しない選び方とおすすめサービス5選を紹介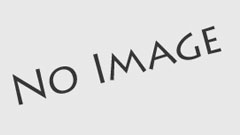 営業DX2024年07月02日営業代行おすすめ5社比較!成功事例と失敗しない選び方をプロが解説
営業DX2024年07月02日営業代行おすすめ5社比較!成功事例と失敗しない選び方をプロが解説 商談マッチングDX2024年05月23日新規開拓営業には戦略が重要!仕組みや手法を知れば成果が上がる
商談マッチングDX2024年05月23日新規開拓営業には戦略が重要!仕組みや手法を知れば成果が上がる弊社の提供する営業DXツールと、オンラインセールス支援サービスにおけるノウハウをカンタンにまとめた資料データを無償配布しております。
是非、皆様の営業にお役立て下さい。